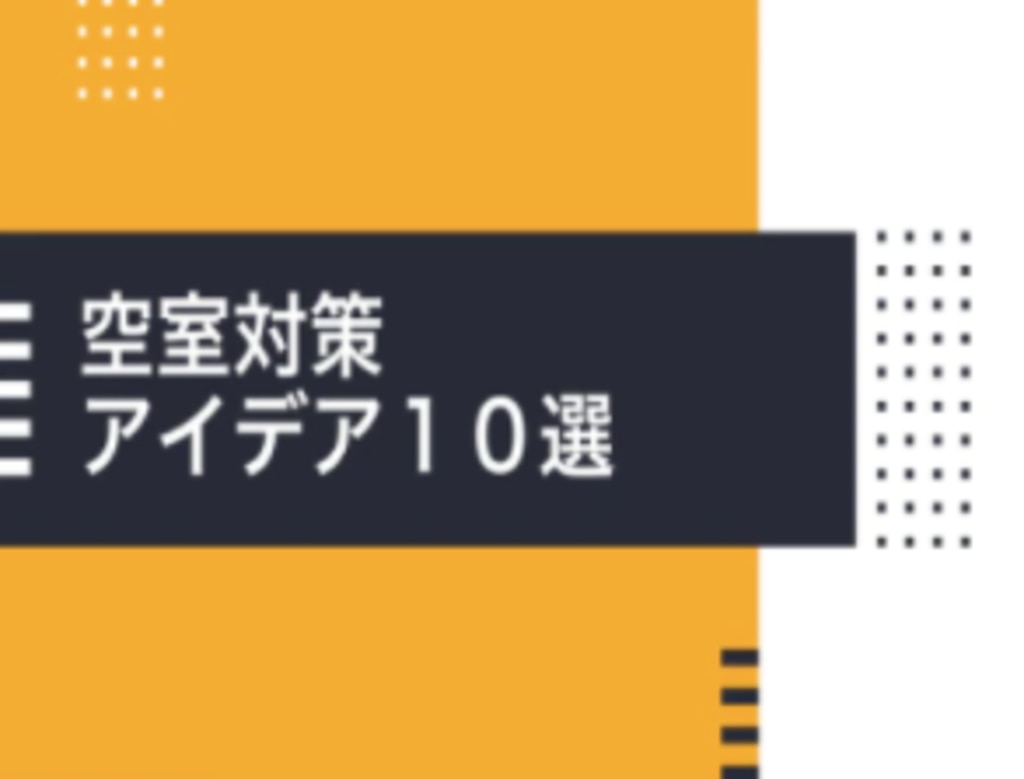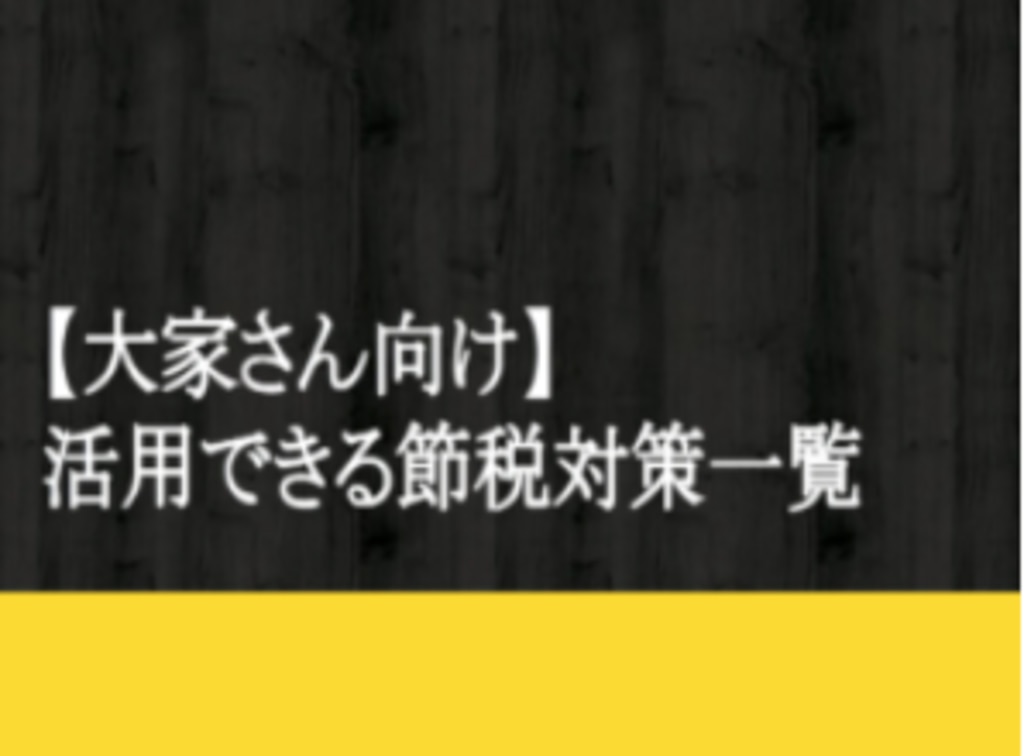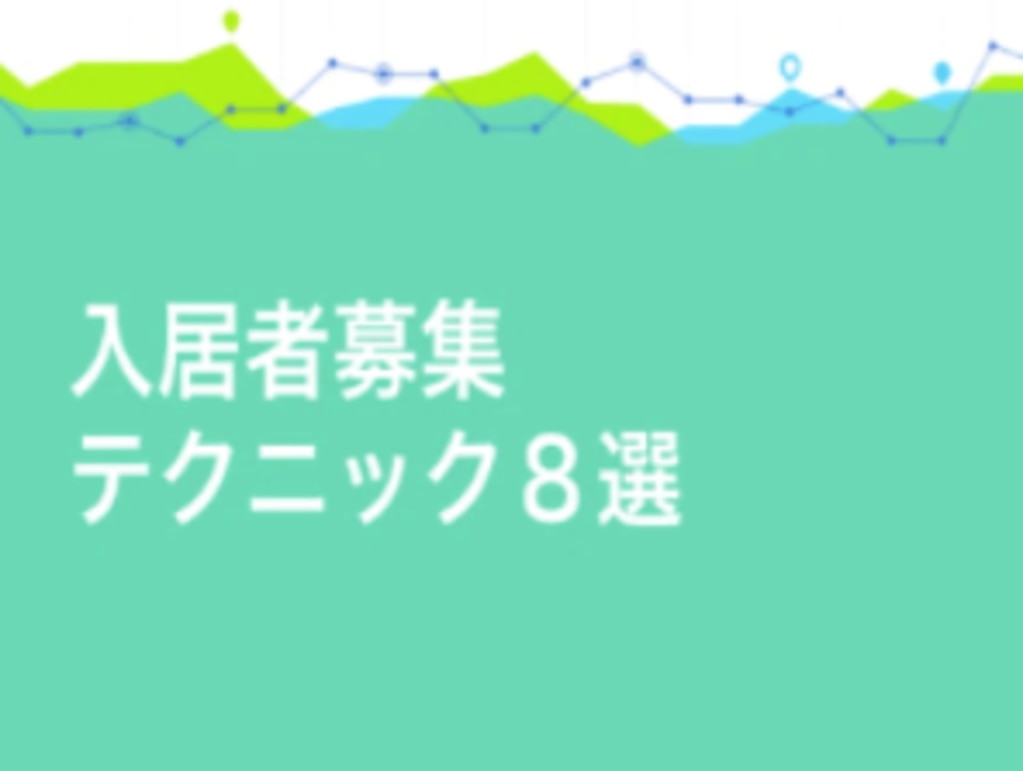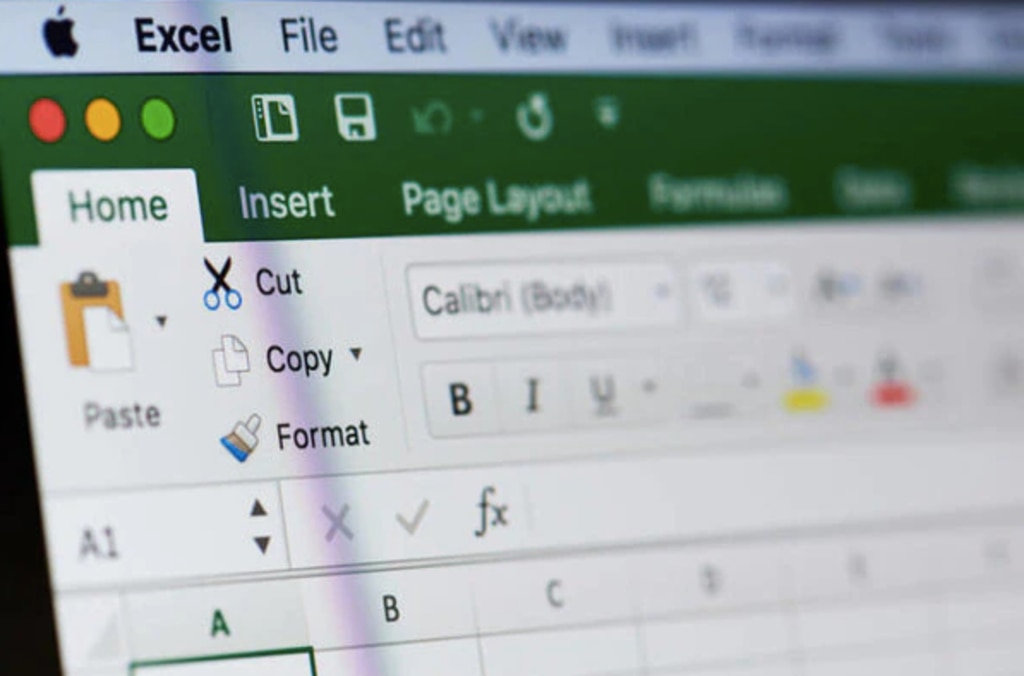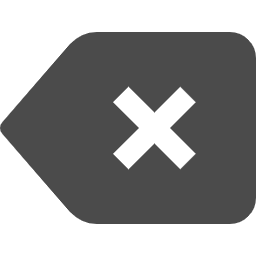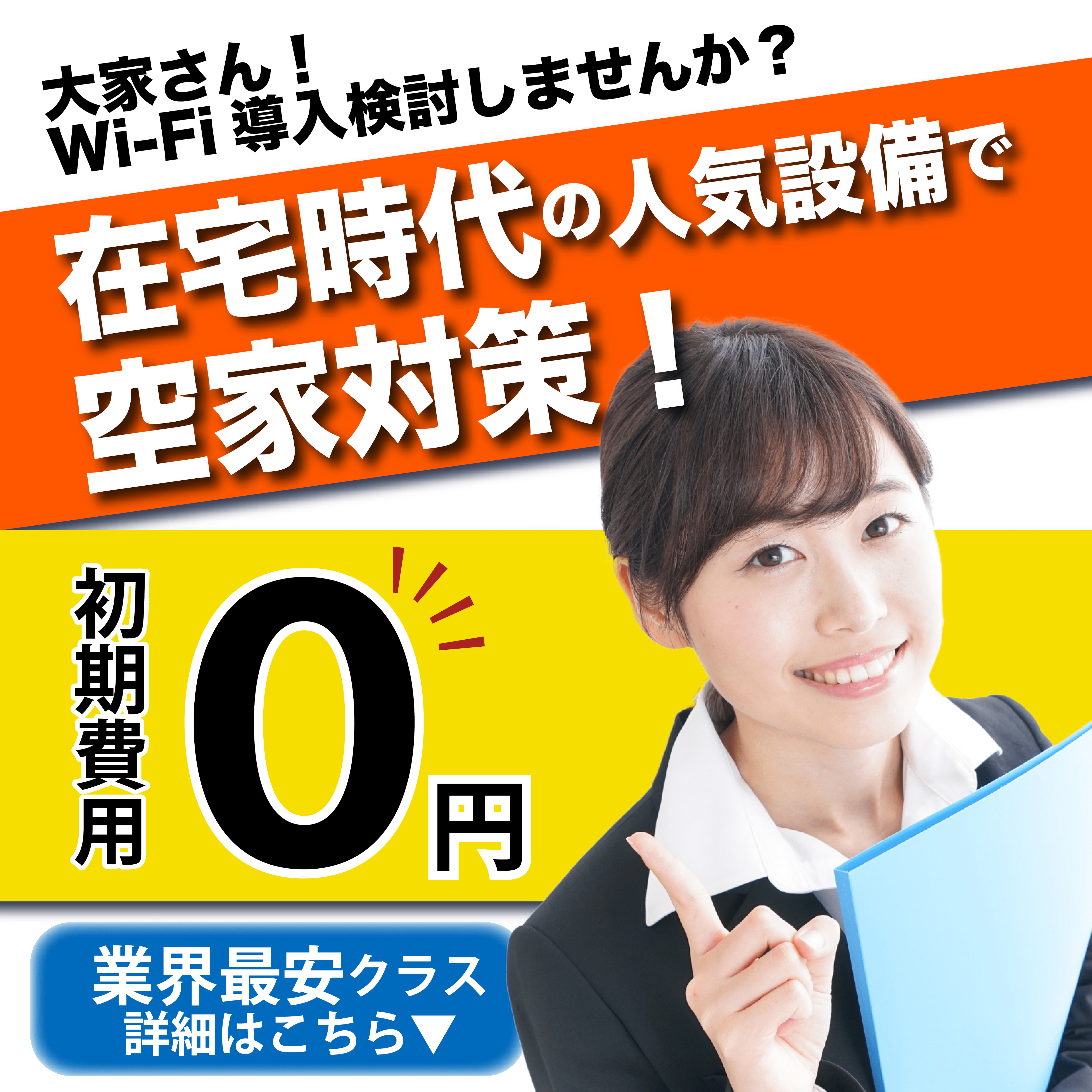アパート経営の利回りの理想と最低ラインは?計算方法・相場と成功するためのポイントを解説!

アパート経営において「利回り」は、投資する物件に対して、どの程度の収益が見込めるかを判断する際の指標のひとつです。
しかし利回りには複数の種類があり、それぞれ役割が異なります。
今回はアパート経営における利回りについて、その種類ごとの役割や注意点について解説します。また利回りの理想と最低ラインの目安も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.アパート経営における利回りの役割と重要性
- 1.1.アパート経営における利回りの役割
- 1.2.アパート経営における利回りの重要性
- 2.利回りの種類と計算方法|表面利回り・実質利回り・想定利回り
- 2.1.表面利回りの計算方法とメリット・デメリット
- 2.2.実質利回りの計算方法と重要性
- 2.3.想定利回りの使い方
- 3.アパート経営における利回り理想と最低ラインの目安は?
- 3.1.新築アパートの利回り目安
- 3.2.中古アパートの利回り目安
- 3.3.土地ありで始めるアパート経営の利回りの優位性
- 4.アパート経営の利回りを判断する際の注意点
- 4.1.実質利回りで判断する
- 4.2.金利上昇を想定して計算する
- 4.2.1.固定金利を選ぶ・変更する
- 4.2.2.繰り上げ返済をおこなう
- 4.2.3.「5年ルール」「1.25倍ルール(125%ルール)」のある金融機関を選ぶ
- 4.3.家賃下落を想定して計算する
- 4.4.業者によって利回りの計算結果が異なるケースもある
- 5.アパート経営で高利回りを維持するためのポイント
- 5.1.空室対策で安定した収入を確保する
- 5.2.適切な管理形態を選ぶ
- 5.3.修繕費を抑える工夫をする
- 6.まとめ
- 7.この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
アパート経営における利回りの役割と重要性

ここではアパート経営において利回りがどのような役割を持つのか、なぜ重要なのかについて解説します。
アパート経営における利回りの役割
アパート経営を含む不動産投資における利回りは、投資する物件に対して、どの程度の収益が見込めるか、また投資した資金を回収するまでの期間などを判断する指標です。
利回りは、投資額の合計に対する年間の利益率を求めるのが一般的です。利回りの数字が高いほど収益効率が高く、短期間で投資額を回収できると考えられますが、同時に高利回り物件にはリスクもあるため注意が必要です。
詳しくは後述する『利回りを判断する際の注意点』で解説します。
アパート経営をはじめ不動産投資で使用する利回りにはいくつか種類があり、よく使われるのは「表面利回り」と「実質利回り」、そして「想定利回り」の3種類です。
それぞれの利回りの違いや計算方法については、後述する『利回りの種類と計算方法|表面利回り・実質利回り・想定利回り』にて詳しく解説します。
アパート経営における利回りの重要性
前述したように不動産投資において利回りは、物件の収益率などを計る際に重要な指標となります。ただし利回りは、さまざまな要素によって変動します。
利回りに影響する要素としては、地価による物件価格の変動や、物件の築年数による家賃が下落したり、突発的な修繕費の発生による支出が増加したりといったことがあげられます。
たとえば、新築・築浅物件は購入価格が高いため、利回りは低めなのが一般的です。その代わり、入居付けがしやすく、また修繕費などを低くおさえることができるため、定期的なメンテナンスや空室対策をしっかりとおこなうことで当初の利回りを維持することにつながります。
反対に物件価格が安くなる築古の中古物件は高利回りが期待できます。ただし、築古物件は入居付けのために家賃を値下げしたり、修繕費が高額になったり、利回りの低下につながる要素が多く、収益が悪化するリスクが想定されるのです。
このように「利回りが高いから」という理由だけで物件を選んでしまうと想定外の支出が嵩んで利回りが下がり、当初想定した収益が得られない可能性もあります。
そのため不動産投資で利回りを利用する際は、利回りの数字だけでなく、築年や物件価格、購入時に発生するリフォーム費などの諸経費、アパート運用時に月々にかかるランニングコストなど、さまざまな要素を踏まえたうえで判断することが重要になるのです。
利回りの種類と計算方法|表面利回り・実質利回り・想定利回り

アパート経営では、主に使用される利回りの種類は「表面利回り」「実質利回り」「想定利回り」の3つです。ここでは、それぞれの違いや計算方法を解説します。
表面利回りの計算方法とメリット・デメリット
表面利回りは、物件の購入価格に対して現行の年間家賃収入の割合を表します。「グロス利回り」と呼ばれることもあります。
表面利回りは、次の計算式で求めます。
表面利回り(%)=年間家賃収入(現行)÷物件購入価格×100
*所有する土地にアパートを新築する場合は、物件購入価格ではなく「建築費」で計算します。
表面利回りのメリットは、購入を検討する物件の収益率を簡単に比較できることです。複雑な計算をする必要がなく、複数の投資対象物件を絞り込む際に便利です。
一方で計算式を見るとわかるように、表面利回りにはアパート経営にかかるランニングコストなどの経費を考慮していません。そのため、実際のアパート経営で得られる利益を正確に計りにくい点がデメリットです。
ポータルサイトや不動産会社などの収益物件の広告に記載されている利回りは、ほとんどの場合でこの表面利回りです。それを知らずに、広告に記載された利回りだけ見て物件を選んでしまい、アパート経営をはじめてみると実際の利回りが表面利回りの半分以下だったというケースもめずらしくありません。
より実際の収益に近い利回りを算出するには表面利回りではなく、次に解説する「実質利回り」を使いましょう。
実質利回りの計算方法と重要性
実質利回りは、年間家賃収入から購入時の諸費用や月々のランニングコストを反映して計算します。そのため表面利回りよりも実際の収益に近い数値を把握できるのがメリットです。
実質利回りは以下の計算式で求めます。
実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間のランニングコスト)÷(物件購入価格+取得時の諸費用)×100
ただし、実質利回りに使用する数字は、あくまでも想定上の数字です。かならずしも実質利回りどおりの収益が見込めるわけではありません。想定外の支出や空室などで、収益が少なくなる可能性があることに留意しておきましょう。
想定利回りの使い方
想定利回りとは、アパートなど複数の部屋がある物件の購入価格に対して、満室での年間家賃収入の割合を表します。
想定利回りは、物件に期待できる最大の利益を求める場合などに使用されるのが一般的です。また不動産広告などにも記載されるケースもあります。
想定利回りは以下の式で計算します。
想定利回り(%)=年間家賃収入(満室状態)÷物件購入価格×100
想定利回りは空室率もランニングコストも考慮されていないため、実際の利益を大幅に上回る数値になりやすく、正確な収益率を判断する際には注意が必要です。
アパート経営における利回り理想と最低ラインの目安は?

実際のアパート経営をおこなうにあたって、目安となる利回りを把握しておきましょう。
ここでは、新築・中古・土地あり・土地なしで始めるアパート経営について、「理想の利回り」と「利回りの最低ライン」を紹介します。
新築アパートの利回り目安
新築アパートの一般的な実質利回りは3%~6%程度のケースが多く見られます。
理想的な利回りは5%程度、最低ラインは3%程度が目安と言われています。
利回りはさまざまな要素で変動するため、目安を一概に述べるのはむずかしいですが、上記の数値がひとつの判断基準となります。
なお、新築アパートは価格が高額なため、中古物件と比べて利回りは低めになるのが一般的です。なお新築物件は、「新築プレミアム」として家賃を相場よりも多少高く設定できますが、特別なメリットのある物件でない限り、大きな差をつけられない場合がほとんどです。
また地域によっても利回りは変動します。通常は、物価の安い地方のアパートの方が物価の高い首都圏よりも高利回りになりやすいです。
しかし地方によっては人口が少なく、賃貸需要自体が少ないケースもめずらしくありません。空室が多い物件を相場よりも安い価格で売りに出しているために高利回りとなっているケースも多いため、あまりにも高利回りの場合は注意が必要です。
中古アパートの利回り目安
中古一棟アパートの利回りは築年数によって差があるため、あくまで目安となりますが、実質利回りの理想は5%~8%程度、最低ラインは4%~7%程度と言われています。
中古アパートの利回りの特徴は、築年数が古くなるほど価格が安くなるため、表面利回りは高くなる傾向にある点です。
その反面、築年数が古いアパートは管理状況が悪く、賃貸に出すために高額の修繕費が必要になったり、賃貸開始後の修繕費も新築アパートと比較して高額になりやすかったり、支出は増加傾向にあります。そのため、表面利回りが高くても、実質利回りはそれほど高くならないことも多いです。
実際、表面利回りが20%超えの超高利回り物件を購入したが、購入後に必要な修繕工事をおこなったら平均的な利回りになってしまったケースも実際にあります。
本当に高利回りの中古アパートを選ぶためには表面利回りの数字だけで判断せずに、購入後に必要となる修繕費やランニングコストなど必要な費用を把握し、実質利回りを計算することをおすすめします。
土地ありで始めるアパート経営の利回りの優位性
相続などで土地を所有している場合、土地活用としてアパート経営をおこなう人も少なくありません。では、所有する土地でアパート経営をおこなう場合、土地なしで始める場合と比較して、表面利回りと実質利回りはどの程度の差があるのでしょうか。
前述したように、新築アパート(土地と建物を購入した場合)の実質利回りの目安は3%~6%程度が目安です。
土地を所有している場合、必要なのはアパートの建築費用のみとなり土地代はかかりません。そのため、通常の新築アパートよりも利回りは高くなります。
例えば、年間の家賃収入が300万円の新築アパートを3,000万円(土地1,500万円、建物1,500万円)で購入したとします。その場合の表面利回りは10%です。
300万円÷3,000万円×100=10%
これと同じ建物を所有する土地に建築した場合の表面利回りは20%となり、土地なしではじめるアパート経営の表面利回りの2倍になるのです。
このように、土地なしに比べて、土地ありで始めるアパート経営は高い収益性が期待でき、非常に有利であると考えられます。
ただし、土地ありでアパート経営をおこなう場合、立地によってはデメリットになる可能性があります。
アパート経営に適した立地条件はいくつかありますが、代表的なのは駅から徒歩10分以内で、周辺にコンビニ・スーパーなどの買い物施設や複数の飲食店がある場合は、「好立地」として高い賃貸需要が期待できます。
そのため、所有する土地が賃貸需要を見込めない、ようするにアパート経営には向かない立地である場合、無理にアパート経営をおこなっても失敗する確率が高くなるため注意が必要です。
所有している土地の活用方法はアパート経営以外にもたくさんの種類があります。どのような土地活用方法が有効であるかは、立地や周辺環境を考慮したうえで検討することをおすすめします。
アパート経営の利回りを判断する際の注意点
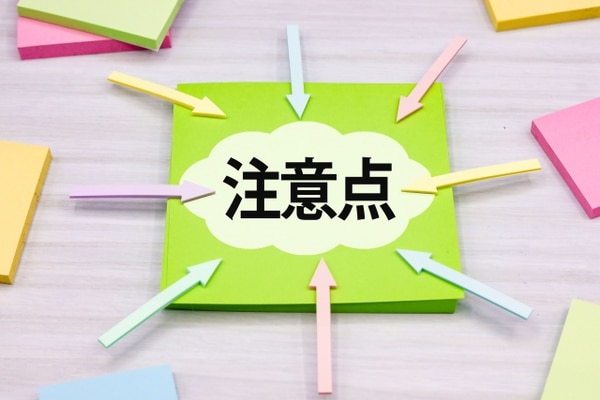
アパート経営における利回りは重要な指標ではありますが、収益性を判断する際は注意したい点がいくつかあります。
- 実質利回りで判断する
- 金利上昇を想定して計算する
- 家賃下落を想定して計算する
- 業者によって利回りの計算結果が異なるケースもある
それぞれについて解説します。
実質利回りで判断する
前述したように、不動産投資における主な利回りには、「表面利回り」「実質利回り」「想定利回り」の3種類があり、それぞれの利回りは役割が異なります。
物件の収益率を比較する際は、購入時の諸費用やランニングコストを反映して計算する「実質利回り」で判断しましょう。
諸費用やランニングコストを反映してしていない表面利回りや想定利回りは、実際の収益よりも大きな数値になることがほとんどです。それらを鵜呑みにしてしまうと、実際の収益がかなり低くなってしまうため注意が必要です。
表面利回や想定利回りは、ポータルサイトや不動産広告などから物件を検索する際の指標のひとつとして利用するのがおすすめです。
金利上昇を想定して計算する
アパートの購入費用を金融機関から借入れる場合、固定金利と変動金利のどちらかを選択します。
現在は低金利なため、固定金利と比べて金利が低い変動金利を選ぶ人が多いです。しかし変動金利は一定期間ごとに金利の見直しがおこなわれ、その時々で金利が変わります。
たとえば金利が上昇した場合、ローン返済額が増えるため利回りは低下します。利回りが低くなることは、すなわち収益の減少を意味するのです。
そのためアパート経営を始める際に利回りの計算をおこなう場合は、金利の上昇を想定したうえで計算しておくことが大事なポイントになります。
高金利の期間にも月々のローン返済を滞りなくおこなえる返済計画を立てましょう。
また実際に金利上昇リスクに備えた対策方法も把握しておく必要があります。代表的な金利上昇のリスク対策方法は次の3つです。
固定金利を選ぶ・変更する
ひとつ目は、融資を受ける際に固定金利を選ぶ、または途中で変動金利から固定金利へ変更する方法です。
固定金利は契約期間内の借入金利が変わりません。そのため金利が上がってもローン返済時の金利は契約時と変わらないため、月々のローン返済額が増える心配はありません。
その代わり変動金利と比較して金利が高く設定されるのが一般的です。
繰り上げ返済をおこなう
手持ちの資金に余裕がある場合は繰り上げ返済をおこないましょう。繰り上げ返済をすることで金利のかかる借入金の元本が減るため、金利上昇によるダメージを抑えることにつながります。
「5年ルール」「1.25倍ルール(125%ルール)」のある金融機関を選ぶ
融資を受ける際、金利上昇時に「5年ルール」「1.25倍ルール(125%ルール)」が適用される金融機関を選ぶとよいでしょう。
「5年ルール」は、金利が上昇した場合でも5年間は毎月の返済額が据え置かれる仕組みです。5年分の上昇した金利の差額については、6年目以降の返済額に上乗せされます。
しかし「5年ルール」が適用されても、6年目以降のローン返済額が高額となり、返済が困難になることも考えられます。
そういった状況を防ぐのが「1.25倍ルール(125%ルール)」です。これは、大幅に金利が上昇した場合でも、返済額は前回の返済額の1.25倍(125%)が上限となる仕組みです。
たとえば毎月10万円のローン返済をしていて金利が上昇して返済額が13万円になったとします。
「5年ルール」が適用された場合、5年間は毎月10万円の返済額のままです。そして6年目からは「1.25倍ルール(125%ルール)」が適用されるので、毎月の返済額は10万円の1.25倍である12.5万円が上限となります。
ただし「5年ルール」「1.25倍ルール(125%ルール)」にも注意点があります。
このふたつのルールは、金利の上昇時に当面の返済額を抑えることはできますが、返済総額が減るわけではありません。
そのため毎月の返済額のうち、金利分が占める割合が増えることで借入金の元本が減らなくなる恐れもあるのです。
もし返済期間が終了しても元本が残る場合は、一括返済もしくは返済期間を延長して返済する必要があります。
5年ルールによって毎月の返済額が据え置かれているあいだに繰り上げ返済をおこなうなど、できるだけ元本を減らしておくことをおすすめします。
家賃下落を想定して計算する
アパート経営では、物件が古くなるにしたがって空室が増えるのが一般的です。その場合、空室を埋めるために家賃を下げて対応することもめずらしくありません。
総務省の研究によると、平均的な家賃下落率は年約1%、10年で1割程度とされています。家賃が10万円であれば、10年後の家賃は9万円に値下がりしてしまうのです。
家賃収入が1割減れば利回りにも大きな影響を与えるため、家賃の下落は決して無視できない要素となります。
アパート経営で利回りを計算する際は家賃の下落を想定したうえで、滞りなく月々のローン返済をおこなえる返済計画を立てましょう。
業者によって利回りの計算結果が異なるケースもある
収益物件を検討する際、物件を扱っている不動産会社が、収益シミュレーションとして利回りの計算をしてくれるケースがあります。
利回りの計算式は一律ですが、計算に使用する数値は業者によって算出方法が異なるため、利回りの計算結果が異なることがあります。
たとえば年間家賃収入は、現在の家賃をそのまま適用するか、相場を基に算出した家賃を使用するかで、利回りの数値が変わります。
また購入時の諸費用やランニングコストに含める項目の種類によっても、計算結果は異なるでしょう。
なお、実質利回りは実際の不動産投資の収益に近い数値を計算できますが、あくまで想定した数字を基に計算したものです。そのため、業者から提供された実質利回りの結果も「これが正しい」とは断言はできません。
収益物件を検討する際は実質利回りの数値だけでなく、物件の周辺環境や競合物件の数、そのエリアの人口動態など、総合的に判断することが大事です。
アパート経営で高利回りを維持するためのポイント
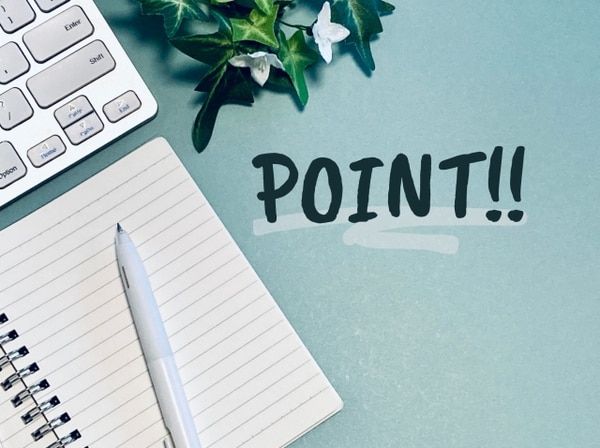
どんなに高利回り物件であっても、経年による賃料の下落や修繕費の増加などによって利回りは徐々にさがっていくのが一般的です。
そのため収益を減らさないためには、高い利回りを維持する必要があります。
ここではアパート経営で高利回りを維持するポイントを解説します。
空室対策で安定した収入を確保する
空室の増加や長期化によって家賃収入が減少すると利回りが下がります。高利回りを維持するためには空室の発生を最小にし、安定した収入を確保するのが重要なポイントです。」
アパート経営における最大の空室対策は、入居者に選ばれる物件を選択することです。利便性が高い好立地であり、入居者ニーズの高い設備を備えたアパートを選びましょう。
またアパート経営後も必要に応じて空室対策をおこないましょう。
しかし空室になる原因はさまざまです。効果的な空室対策をおこなうためには、まず原因を明らかにする必要があります。
たとえば設定した家賃が相場よりも高額だった場合は、相場に沿った家賃にすることで入居者が見つかる可能性が高くなります。
共用部の清掃が不十分の場合、内見時の印象が悪く、入居に結び付きにくくなりますし、既存の入居者の満足度の低下にもつながります。日常的な清掃の頻度を増やしたり、汚れや劣化が著しい箇所に関しては、高圧洗浄をしたり、修繕や交換で対応したり、清潔さと安全性を確保しましょう。
また、防犯カメラやオートロックなどを設置してセキュリティ面を強化したり、宅配ボックスや24時間ゴミ出しOKなど利便性を上げたり、入居者にとってプラスになる設備を導入するのも効果的な空室対策につながります。
また入居者の募集を不動産会社に依頼している場合は、積極的に入居付けをおこなってもらえるよう、日頃から良好な関係を築いておきましょう。
適切な管理形態を選ぶ
アパート経営で安定した家賃収入を得るためには、建物の管理や入居者管理は欠かせません。管理が適切におこなわれなければ既存入居者の不満が高まり、退去につながるおそれがあります。また入居者の募集にも悪影響を及ぼします。
収益物件の管理形態は、主に以下の3種類あり、それぞれメリットとデメリットがあります。
- 自主管理
- 管理委託
- サブリース
ひとつ目の自主管理は、すべての管理業務を大家さん自身でおこないます。管理委託手数料がかからないため支出を抑えられ、利回りが高くなるのがメリットです。
ただし、契約関連の手続きや入居者からのクレーム対応、建物や設備の修繕・メンテナンスの実施・手配など、すべての管理業務を大家さん自身でおこなわねばならず、時間や体力的な負担が大きいのがデメリットです。
サラリーマン大家さんのように、本業を持っている人に自主管理によるアパート経営をおこなうのは現実的にむずかしいと言えるでしょう。
ふたつ目の管理委託は、管理業務の全部または一部を不動産管理会社に委託する方法です。その場合、不動産管理会社へ管理委託手数料として賃料の5%~8%程度のコストが発生するため、その分、利回りが下がるのがデメリットです。
メリットは、大家さんの負担が大幅に軽減するため、本業を持っている人でも無理なくアパート経営をおこなえる点にあります。
3つ目のサブリース契約は、サブリース業者(不動産会社)がアパートを丸ごと一括で借り上げて、入居者へ転貸しする仕組みです。管理業務全般のサブリース会社がおこないます。
サブリースの最大のメリットは空室の有無に関わらず賃料が保証される点です。
ただし、保証される賃料の一部は管理委託手数料としてサブリース業者が徴収するため、通常の賃貸経営で満額時の家賃収入と比較して利回りが低くなるのがデメリットです。なお、サブリースの管理委託手数料の相場は家賃の10%~20%程度になります。
またサブリースの家賃保証は定期的に見直されるのが一般的です。空室率や経年によって保証される家賃が下落することもめずらしくなく、場合によってはキャッシュフローが赤字になるケースもあるため注意が必要です。
いずれの管理形態にもメリットとデメリットがあるため、一概にどれが良いとは決められません。
利回りだけで考えればコストのかからない自主管理が良いように見えますが、管理が行き届かず入居者の不満が募ると空室の原因になってしまうおそれがあります。
高利回りを維持するためには、物件の規模や大家さんのアパート経営の経験値、時間的な制約などさまざまな観点から見て、現況にもっとも適切な管理形態を選択することが高利回りの維持につながるでしょう。
修繕費を抑える工夫をする
修繕費はアパート経営のランニングコストの中でも大きな割合を占める重要なポイントです。
特に築年数が経過したアパートは、建物や設備の老朽化を防ぐためにおこなうメンテナンスや修繕が欠かせません。
特に10年~15年周期でおこなう、屋根の防水工事や外壁の改修・塗装、給排水管の高圧洗浄・交換などの大規模修繕は、アパートの資産価値を維持するために欠かせない工事です。しかし大規模修繕には高額の費用がかかります。
大規模修繕に必要な費用は、アパートの規模や構造、修繕箇所によって異なりますが、1戸当たり約7万円~80万円と高額です。
大規模修繕をおこなった年は高額の修繕費が発生するため、収益は減少するのが一般的です。
大規模修繕をおこなわなければコストの節約にはなります。しかし大規模修繕をおこなわずにいると、建物が傷んで雨漏りしたり、排水管の水漏れしたり、物件の価値の低下や入居者からのクレームにつながり、結果的に空室リスクが高まります。
空室が増えて家賃収入が減ると利回りが大きく下がるおそれがあります。
空室リスクを避けるためにも大規模修繕を欠かすことはできませんが、できるだけ大規模修繕費を削減することで、利回りの低下を防ぐことは可能です。
大規模修繕費の削減方法としては、建物や設備に大きな傷みや不具合が発生する前に対処することがあげられます。
日常の定期点検を実施し、傷みや不具合が小さなうちに適切な処置をおこなうことで、少ない修繕費で済むだけでなく、大規模修繕の周期を引き延ばすことにつながります。
また定期点検以外にも、台風やゲリラ豪雨などの自然災害のあとは、念入りに建物や設備を確認し、適切な修繕をおこなうとよいでしょう。
まとめ
アパート経営にて使用される利回りは複数の種類がありますが、実際のアパート経営の収益率により近い数値を求める際は、諸費用やランニングコストを反映させて計算する実質利回りを用いましょう。
ただし利回りの計算は、想定上の数字を使って計算するため、かならずしもその物件の収益を保証するものではないことに留意したうえで利用する必要があります。
また利回りは、地域や築年数、物件価格などによって変動します。
アパート経営の成功には物件の選定が大きく左右します。物件を選ぶ際は利回りの数値だけでなく、物件の状態や周辺環境、賃貸需要などをしっかりと確認したうえで、総合的に判断することが大事です。
この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
>>カテゴリー別おすすめアパート建築会社一覧
>>大家さん必見の空室対策アイデア10選
>>アパートWiFi導入のメリット&デメリット
>>入居者募集テクニック8選