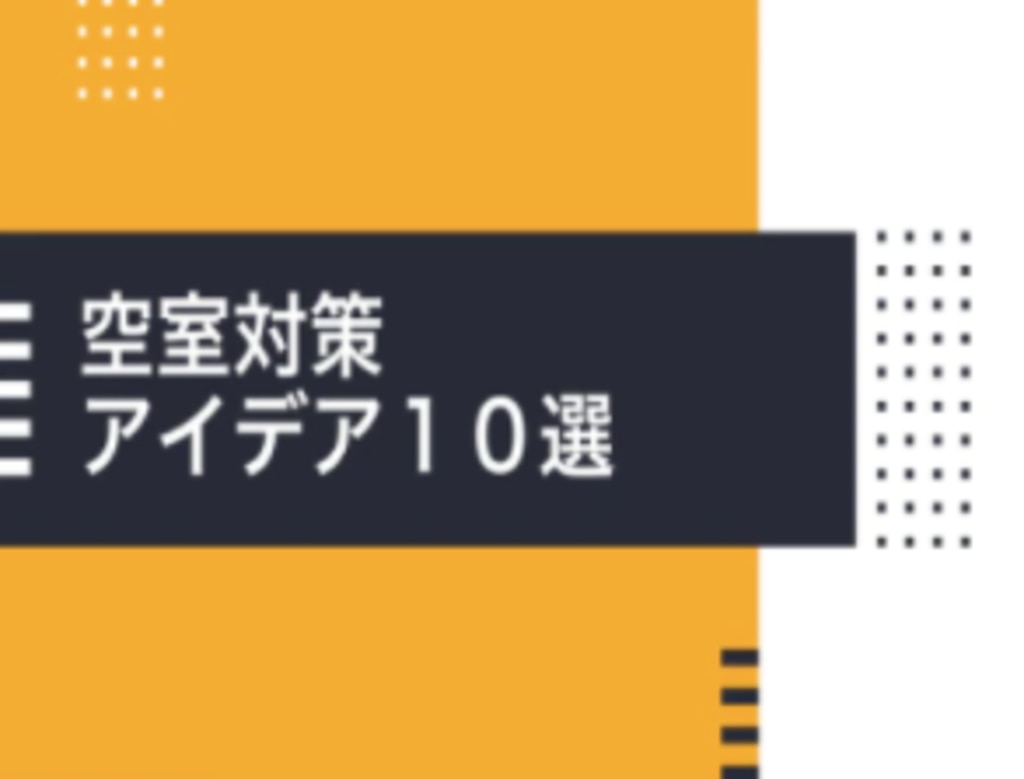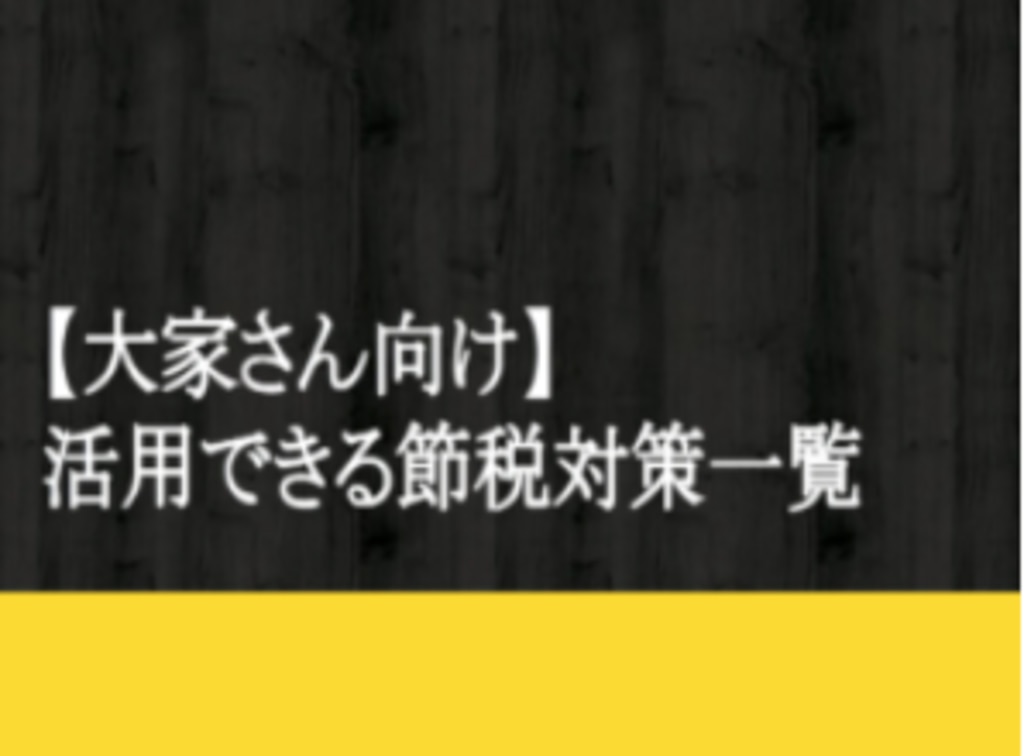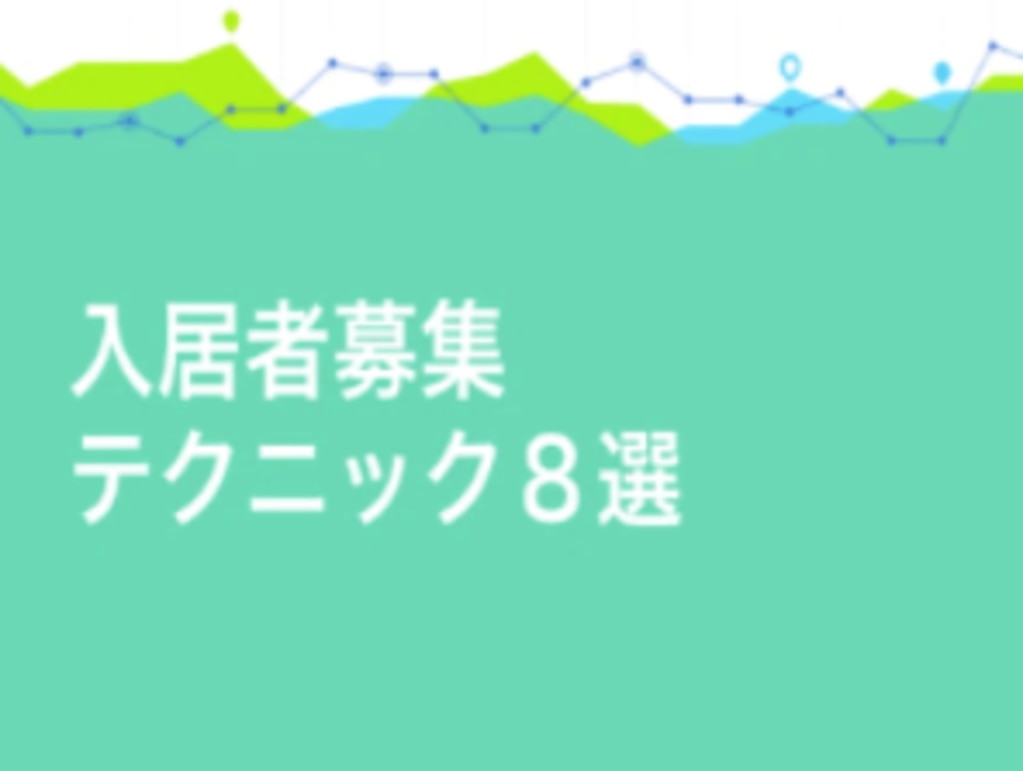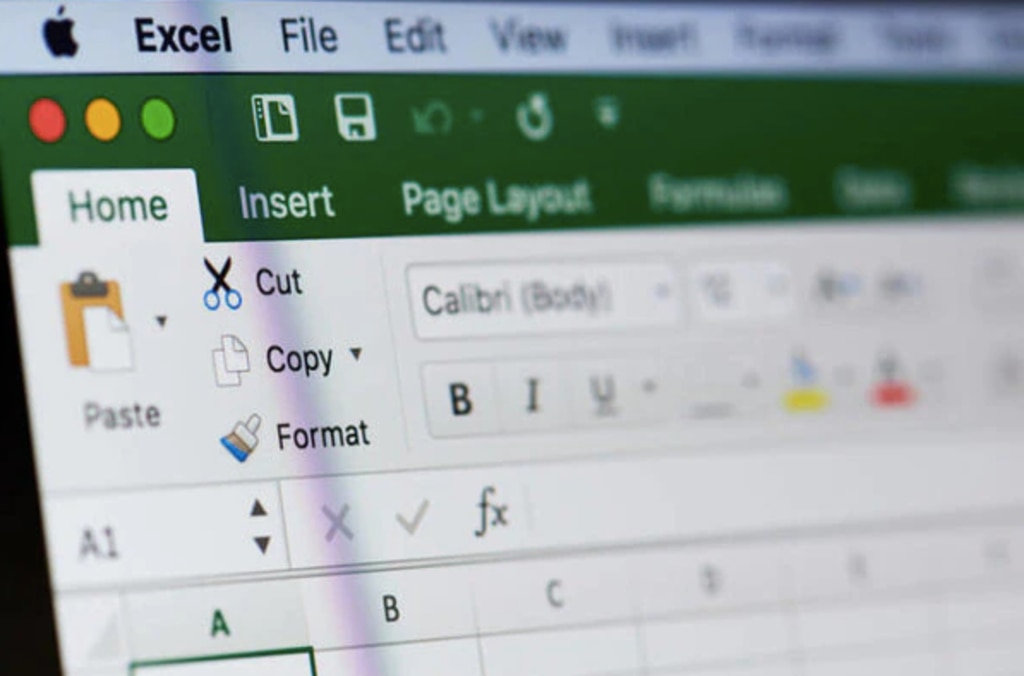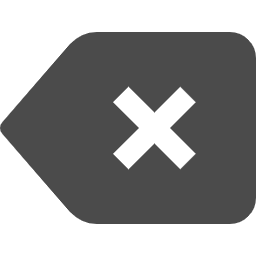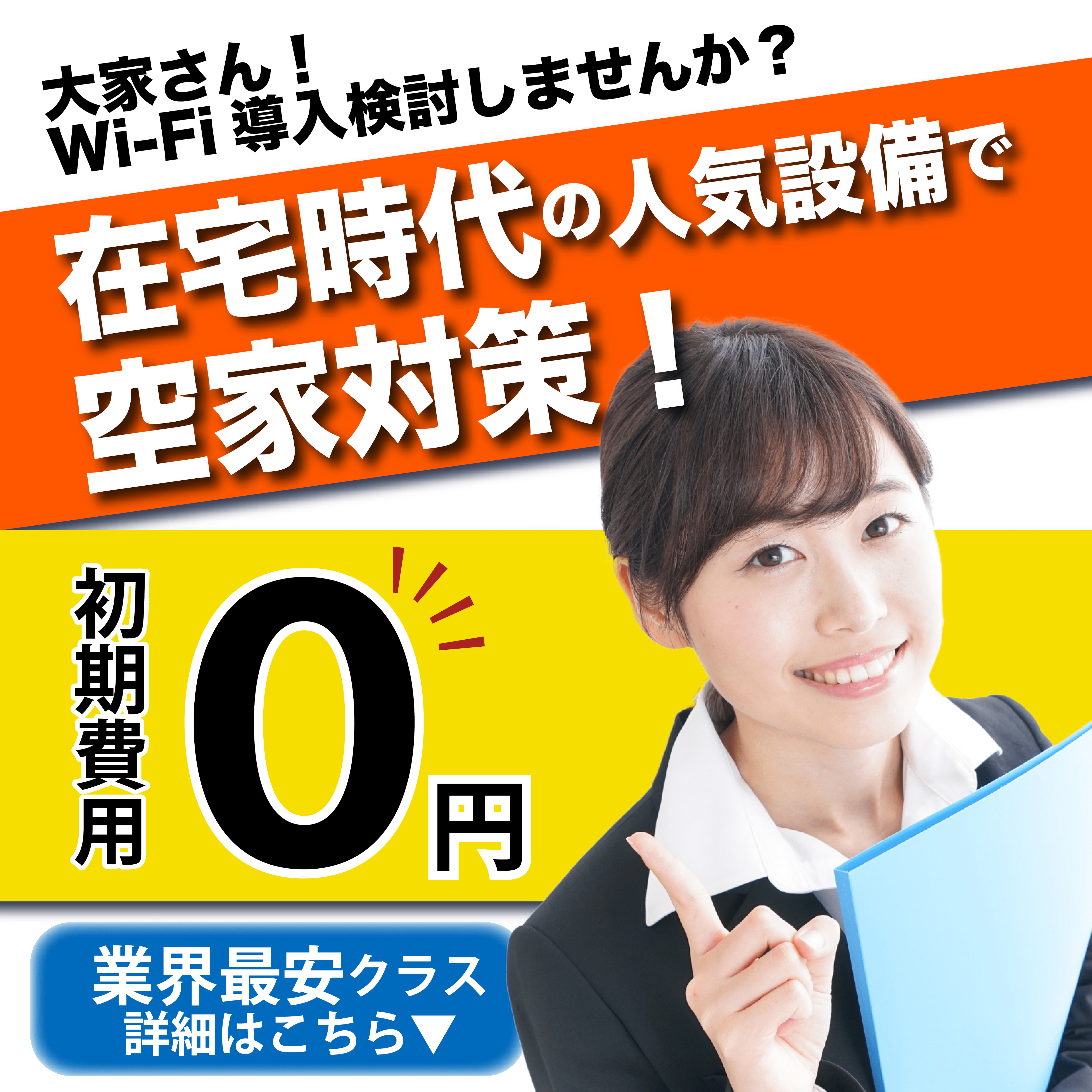工事現場でのデジタルサイネージ活用法と失敗しない設置のコツを解説!

「デジタルサイネージ」とは、ディスプレイやモニターに動画や画像コンテンツを表示することができる電子看板のことです。
主に街頭やショッピングセンターの店舗などで宣伝・広告用として目にする機会が多いデジタルサイネージですが、近年は工事現場や建築現場で活用されるケースが増えています。
はたして工事現場にデジタルサイネージを設置・活用することで、どのようなメリットが生まれるのでしょうか。
今回は工事現場でデジタルサイネージが活用される理由や具体的な活用事例、設置する際の注意事項などを解説します。
目次[非表示]
- 1.デジタルサイネージとは?
- 2.工事現場でデジタルサイネージが活用される理由
- 2.1.①DX化の推進
- 2.2.②作業の安全性向上と健康維持
- 2.3.③SDGs目標の達成
- 3.工事現場で活用されるデジタルサイネージの種類
- 3.1.屋内用デジタルサイネージ
- 3.2.屋外用デジタルサイネージ
- 3.3.仮囲い用デジタルサイネージ
- 3.4.顔認証と検温機能付きデジタルサイネージ
- 3.5.タッチパネル式デジタルサイネージ
- 4.デジタルサイネージのコンテンツ発信方法
- 4.1.タブレットなどの端末とのミラーリング機能
- 4.2.メディアプレイヤー機能内蔵タイプ
- 4.3.CMS(コンテンツ管理システム)の活用
- 5.工事現場のデジタルサイネージ設置における注意点
- 5.1.デジタルサイネージ(液晶ディスプレイ)設置に必要なもの5つ
- 5.1.1.①100V専用電源
- 5.1.2.②防水ゴムボディ
- 5.1.3.③単管と専用金具
- 5.1.4.④付属品の保管スペース
- 5.1.5.⑤表示用コンテンツの準備
- 5.2.デジタルサイネージ設置時の注意点
- 5.2.1.発電機は基本的に使えない
- 5.2.2.設置場所にあったディスプレイを選ぶ
- 5.2.3.画面破損が一部でも本体交換が必要
- 6.デジタルサイネージの設置でよくある失敗と対策
- 6.1.設置用の単管が準備されていない
- 6.2.電源回路の不足
- 6.3.防水ゴムボディのケーブルが短い
- 6.4.液晶ディスプレイは時間帯によって画面が見えにくい場合がある
- 6.5.破損には要注意
- 7.まとめ
- 8.この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
デジタルサイネージとは?

「デジタルサイネージ」とは、液晶ディスプレイやLEDディスプレイなどの電子媒体を使って広告やニュースなどの情報を表示・発信するシステムのことです。
サイネージ(signage)は看板や標識を意味し、「デジタル看板」や「電子看板」とも呼ばれます。
デジタルサイネージは屋外・室内を問わず、さまざまな場所に設置が可能です。
発信する情報はデータ化されたものを用いるため、インターネット通信を利用すれば遠隔地から最新の情報をリアルタイムで表示・更新することも簡単におこなえるため、デジタルサイネージを採用する店舗や企業、病院や建築・工事現場でも利用するケースが増えています。
デジタルサイネージの活用事例
デジタルサイネージはさまざまな場所で、いろいろな方法で活用されています。
ここではデジタルサイネージの活用例を具体的に紹介します。
商業施設での活用
大型ショッピングセンターや百貨店をはじめ、テナント、小規模な路面店など、規模や業種を問わずさまざまな店舗でデジタルサイネージが活用されています。
商品の紹介をはじめ、セール情報を時間帯にあわせて表示したり、季節ごとのイベントの告知に利用したり、販売促進のために幅広く活用されています。
またショッピングモールや百貨店では、タッチパネル式のサイネージを利用した館内案内や店舗情報を配信するケースも多いです。
飲食店ではテーブルごとにタブレット端末を設置し、メニュー情報の発信とともに商品の注文ができる「タブレットオーダーシステム」を採用するケースも増えています。
販売促進につながるだけでなく、利用客が直接システムに入力するため注文ミスが減り、スタッフの負担が軽減するため人件費の削減にも効果が期待できます。
交通機関での活用
駅やバスターミナル、空港などの交通機関では、時刻表の表示のほか、乗り場や施設内の案内、運航状況・遅延情報の発信などにデジタルサイネージを用いる例が増えています。特に運行状況や遅延情報はリアルタイムでの発信ができ、利用者の利便性を高める効果につながります。
周辺の観光情報などを発信するケースも多く、交通機関の利用者の利便性向上に加えて、スタッフの業務負担を軽減することも可能です。
またバスや電車、タクシーの車内に設置した小型モニターに広告や映像を表示するなど、幅広くデジタルサイネージが活用されています。
医療機関での活用
病院や薬局などの医療機関でもデジタルサイネージが導入・活用されています。
受付や待合室などにモニターを設置し、診療時間や休診日、診療科目などを表示したり、季節に合わせた健康情報を発信したりすることで受診者への情報提供が可能です。
また、デジタルサイネージと呼び出しシステムを導入することで、受診者が診察順番や番号を確認しやすくなるとともに、受診の待ち時間対策に効果が期待できます。
そのほかにも院内マップやの案内を表示するなど、さまざまな方法で受診者のサポートにためにデジタルサイネージが活用されています。
デジタルサイネージ専用デバイスと家庭用モニターの違い
基本的にデジタルサイネージを利用する場合は専用のディスプレイが必要です。
しかし中には、一般家庭で使用する安価なテレビをディスプレイ代わりにできないかと考える人もいるでしょう。
結論から言うと、デジタルサイネージをテレビで代用することは可能ですが、設置場所が限定される可能性が高いです。
テレビとデジタルサイネージ専用ディスプレイの最大の違いは「輝度」にあります。
デジタルサイネージは多くの人の目に留まることを目的としているため、テレビに比べて画面の輝度が高いのが特徴です。
デジタルサイネージは、ディスプレイの輝度が低いと周辺の明るさに負けてしまい画面が暗くなり、映像が見えなくなってしまうのです。
デジタルサイネージ専用ディスプレイの輝度は、屋内用で350~1000カンデラ/㎡、屋外用で1200~2500カンデラ/㎡程度の輝度が備わっています。(なお、カンデラ/㎡とは輝度を示す単位で、数値が大きいほどより明るくなります)
特に屋外の場合、直射日光が当たると画面がほとんど見えなくなることもあるため、輝度が高いディスプレイが必要になります。
一方、一般的な家庭用TVの輝度も350~500カンデラ/㎡程度です。この数値では、日中の屋外では画面がほとんど見えません。屋内であればテレビをデジタルサイネージとして使用可能ですが、屋内でも周囲が明るい場所では画面が見えにくくなるため注意が必要です。
輝度の問題以外にも、テレビをデジタルサイレージとして使用する場合は以下のようなデメリットがあります。
- 防水加工がされていないため屋外で使用すると故障の原因になる
- 縦に置くことができない
- 衝撃に弱く破損のおそれがある
- 再生用プレイヤーやケーブルなどの周辺機器が別途必要になる
デジタルサイネージの設置場所や利用目的によっては、やはりデジタルサイネージ専用のディスプレイの方が手間やコストがかからず安心して利用できるでしょう。
どうしてもテレビをデジタルサイネージとして使用するのであれば、以上の点を留意したうえで、自己責任で使用することをおすすめします、
工事現場でデジタルサイネージが活用される理由

さまざまな場所や業種で活用されているデジタルサイネージですが、最近では建設現場や工事現場で利用されるケースが増えています。
ここでは、建築現場や工事現場でデジタルサイネージが活用される理由や活用例を紹介します。
①DX化の推進
デジタルサイネージを活用することで、建築・工事現場のDX化(デジタルトランスフォーメーション化)の推進につながります。
工程表や作業内容など、これまで紙媒体で掲示していたあらゆる通達事項の共有が素早くかつ効率的におこなえます。
特にスケジュールや作業内容に変更があった場合、修正した情報を遠隔操作で即座にデジタルサイネージに表示することが可能です。印刷・掲示といった手間が省けるだけでなく通達までのタイムロスを防げるため、業務の効率化や作業ミスの減少が期待できます。
②作業の安全性向上と健康維持
デジタルサイネージを工事現場に導入することで、安全のための情報を従業員に向けて配信することが可能です。
工事現場では作業員の安全と健康のため、「立ち入り禁止区域」や「禁止行為」などの安全管理を徹底させる必要があります。また基本的に屋外での作業になるため、夏場は熱中症への注意喚起なども欠かせません。
しかし、工事現場に通常の掲示板を設置しても紙に印刷された情報すべてに目を通すのは時間がかかることもあり、周知がむずかしいケースもあります。
そこで、従来の掲示板をデジタルサイネージに変更し、安全や健康についての情報を繰り返し表示させることで、ひとつひとつの情報が自然と目に入りやすくなるため情報共有の精度が上昇し、結果的に安全管理につながります。
③SDGs目標の達成
デジタルサイネージを工事現場に導入することで、SDGs(持続可能な開発目標)に関するいくつかの目標を達成することにつながります。
たとえば、デジタルサイネージを使用することで紙の消費を大幅に削減できます。すると紙の原料となる森林の保護や、紙を製造する過程で発生するCO2排出の削減など、環境負荷を低減することが可能です。
また、前述したようにデジタルサイネージを活用して業務上の通達事項を素早く共有することで生産性の向上や、作業員の安全と健康を守る情報を発信することで、安全に作業できる現場作りの推進に貢献します。
工事現場で活用されるデジタルサイネージの種類
デジタルサイネージはさまざまな業種で活用されていますが、工事現場に導入されるのはどのような種類のものが見られるのでしょうか。
ここでは工事現場で活用されているデジタルサイネージの種類や機能の活用例を紹介します。
屋内用デジタルサイネージ
工事現場内に用意された仮設事務所内のほか、作業員用の休憩所など室内に設置されます。
比較的小型のディスプレイが好まれ、仮設事務所では主にミーティングなどに利用されます。パソコンやタブレットなどから簡単に情報を送信でき、その場でデータを修正して即座に共有できます。
作業員用の休憩所などに設置するデジタルサイネージには、従業員の安全や健康に配慮した情報を掲示するのが一般的です。
立ち入り禁止区域を示す図面や天気予報、熱中症への注意喚起などの情報を発信することで現場全体の安全性の向上につながります。
なお、屋外に設置したデジタルサイネージと同期できるので、同じ内容を掲示することも簡単におこなえます。
屋外用デジタルサイネージ
主に現場の朝礼の際、工程や作業内容の確認・変更など、情報共有目的で使用されます。朝礼以外の時間帯には、立ち入り禁止区域や天気予報、熱中症予防などの情報を切り替えながら発信することで、従業員が安全に作業できる現場作りに役立てます。
なお屋外に設置するサイネージは、防水・防塵機能を備え、直射日光下でも鮮明に映像を表示できる輝度の高い機種が求められます。
また一度に多数の従業員に情報を届けられるよう、視認効果が高く広範囲に音声を流せる大型デジタルサイネージが設置されるケースが多いです。
仮囲い用デジタルサイネージ
周辺の住民に向けた情報発信のため、仮囲い用掲示板として活用されます。
円滑に工事を進めるためには周辺の住民との良好な関係を保つことが非常に重要です。
そこで従来の掲示板の代わりに小型の屋外用デジタルサイネージを活用し、工事の詳細(着工日と竣工予定日、建築主や施工者など)や、建物の完成予定図を掲示することで周辺住民から理解してもらいやすくなります。
また工事に関して変更があった場合、デジタルサイネージであればリアルタイムで情報の修正・発信も可能です。
このように工事に関する近隣トラブルを防止するためにも、デジタルサイネージの設置が有効な手段となります。
顔認証と検温機能付きデジタルサイネージ
工事現場の入り口に顔認証と検温機能付きのデジタルサイネージを活用することで、感染症対策に効果が期待できます。
たとえば、デジタルサイネージと入口の電子錠を連動させ、一定の体温を超えると電子錠が解除できないように設定します。そうすることで感染症の予防につながり、同時に従業員の健康管理もおこなえます。
タッチパネル式デジタルサイネージ
タッチパネル式のデジタルサイネージは、図面や工程表などを見る際に重宝します。
画面にタッチするだけで図面の一部を拡大縮小したり、スワイプして必要な箇所を表示したり、必要な情報の確認が短時間でおこなえます
デジタルサイネージのコンテンツ発信方法

ここでは、デジタルサイネージにコンテンツを発信するための方法などを紹介します。
タブレットなどの端末とのミラーリング機能
デジタルサイネージは、タブレットやスマートフォン、パソコンなどの端末とのミラーリングが可能です。ミラーリングとは、各端末上のデータをデジタルサイネージに映し出す機能を言います。
手元にあるタブレットなどの端末で編集・修正したデータを、簡単かつ素早くデジタルサイネージに映し出せるので、工事現場でのミーティングなどにおすすめの機能です。
メディアプレイヤー機能内蔵タイプ
デジタルサイネージには、メディアプレイヤーが内蔵されたタイプもあります。
SDカードやUSBメモリをデジタルサイネージに直接差し込むことで映像や画像を映し出すことができるので、Wi-Fi環境がない現場でもデジタルサイネージを活用できます。
CMS(コンテンツ管理システム)の活用
CMSとは「コンテンツ・マネジメント・システム」の略称で、デジタルサイネージに配信する動画や画像などのコンテンツを管理するためのソフトウェアのことです。
CMSを活用することで配信スケジュールの設定、配信する順番や表示する秒数などの管理が簡単におこなえます。
また遠隔操作も可能なので、複数台のデジタルサイネージでコンテンツを共有する際もCMSを利用することで手間なく一括配信ができます。
工事現場のデジタルサイネージ設置における注意点

ここでは、工事現場に液晶タイプのデジタルサイネージを設置するにあたって必要な備品と注意点を紹介します。
デジタルサイネージ(液晶ディスプレイ)設置に必要なもの5つ
下記は液晶ディスプレイのデジタルサイネージを設置する際に必要なものです。ただし、ディスプレイの種類や設置場所、設置方法によっては必要なものが異なる場合があるため注意しましょう。
①100V専用電源
デジタルサイネージを設置する際は100Vコンセントの確保が必要になります。
その場合、周辺機器用の電源と共用してしまうと火災などの原因になるおそれがあるため、1台にひとつ、かならず専用電源として確保しましょう。
なお、デジタルサイネージの種類によっては、対応電源が異なるためご注意ください。
②防水ゴムボディ
デジタルサイネージの電源ケーブルを直接ブレーカーに接続するためには電気工事士の資格が必要です。しかしそれでは、デジタルサイネージを移設する際に取り扱える人が限られてしまい不便です。
そこで、伊勢辻などに簡単にプラグを抜き差しできるように防水ゴムボディを設置しましょう。
防水だけでなく防塵効果もあるので、屋外にデジタルサイネージを設置する際もおすすめです。
③単管と専用金具
工事現場にデジタルサイネージを設置する方法はいくつかありますが、工事現場にかならずある「単管」と「サイネージ固定用専用金具」を利用するのが一般的です。
ディスプレイの大きさや設置場所にあわせた数を用意しましょう。
なお、設置後のデジタルサイネージのがたつきを抑えるために、単管は1本物が望ましいです。
④付属品の保管スペース
屋外にデジタルサイネージ本体以外の周辺機器(マルチメディアプレーヤーなど)を設置する場合、機器を入れた防水ボックスを置くスペースが必要になります。デジタルサイネージ本体の背後などに設置するのが一般的です。
⑤表示用コンテンツの準備
工事現場に設置したデジタルサイネージに表示させるコンテンツの準備が必要です。
現場にあわせて、どのようなコンテンツを配信するか検討しましょう。
コンテンツの作成は、PowerPointなどを使用して自社で作成するほか、デジタルサイネージ専用コンテンツの制作会社に依頼することも可能です。
また天気予報やニュースなどをデータ形式で自動配信するサービスを利用することもできます。
ただし、コンテンツの作成やデータの自動配信サービスを利用するためには別途料金が必要です。
デジタルサイネージ設置時の注意点
デジタルサイネージを工事現場に設置する際は、以下のポイントに注意しましょう。
発電機は基本的に使えない
屋外にデジタルサイネージを設置する際、電源に発電機を検討するケースがあります。しかし発電機を電源にした場合、電気の安定供給ができず機器の故障につながる可能性が高く大変危険です。
電源確保がむずかしい場合は、ソーラー発電を活用したデジタルサイネージなどを検討すると良いでしょう。
設置場所にあったディスプレイを選ぶ
工事現場にデジタルサイネージを導入する際は、設置場所にあったディスプレイを選ぶ必要があります。
屋内か屋外かはもちろん、画面の大きさや輝度、耐久性などが設置場所にあっていないと画面が見えにくかったり、故障や不具合が頻繁に発生したり、デジタルサイネージを導入した意味がなくなってしまいます。
画面破損が一部でも本体交換が必要
液晶ディスプレイは画面の一部が破損・故障してしまうと本体ごと交換しなければなりません。そのため取り扱いには細心の注意が必要です。
特に工事現場はさまざまな道具や重機が使用されるため、液晶ディスプレイを設置する際は、安全な場所を選びましょう。
なお、LEDディスプレイは画面の一部が破損しても、その部分のパネル交換だけで対応することが可能です。
デジタルサイネージの設置でよくある失敗と対策
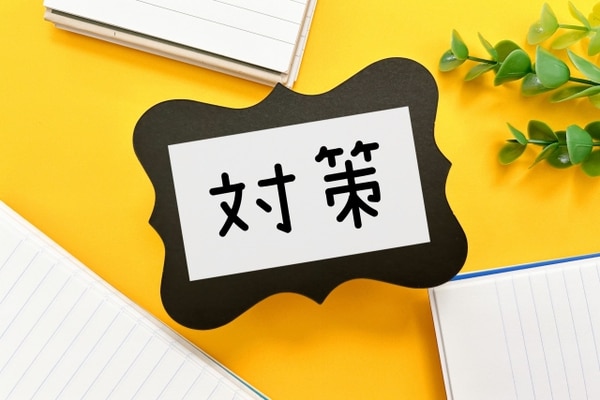
ここでは、工事現場にデジタルサイネージを導入する際によくある失敗と対策方法を紹介します。
設置用の単管が準備されていない
単管を使ってデジタルサイネージを設置する際は、必要な本数の単管と専用の専用金具が必要です。
デジタルサイネージのディスプレイが搬入されても、設置用の単管や専用金具が用意されていないと、当日中の施工がデキなくなる場合もあります。
工事現場にデジタルサイネージを設置する際は、あらかじめ設置に必要な資材を用意しておきましょう。
電源回路の不足
デジタルサイネージが液晶ディスプレイの場合、稼働のために100Vの電源が必要です。
工事現場で使用する電源については、あらかじめ専門の電気工事会社に相談しておくことが大事です。
なお、安全のためにタコ足配線は避け、専用の電源を確保しましょう。
防水ゴムボディのケーブルが短い
デジタルサイネージのディスプレイを電源に接続する際は防水ゴムボディを利用しますが、用意したケーブルが短くて届かないケースがあります。
このケーブルが短すぎて届かないという事例も発生しています。
防水ゴムボディ用のケーブルを準備する際は、あらかじめ必要な長さを図ったうえで、十分な長さのケーブルを用意しておきましょう。
液晶ディスプレイは時間帯によって画面が見えにくい場合がある
デジタルサイネージは、設置場所によって必要とする輝度が異なります。特に屋外に設置する場合は直射日光に当たっても画面がしっかりと見えるよう、輝度の高いものがほとんどです。
しかし、液晶ディスプレイは画面の表面に強化ガラスが貼られているため直射日光が反射しやすく、コンテンツが見えにくくなるケースがあります。
そのため、屋外の工事現場に液晶ディスプレイを設置する際は設置予定の位置やデジタルサイネージの稼働時間帯などから、日光の支障のない場所を選ぶと良いでしょう。
破損には要注意
デジタルサイネージとして小型の液晶ディスプレイを導入した場合、コンテンツをよく見ようとして画面の前に人が集まりがちです。その際、作業員が腰に付けている道具などがディスプレイに当たり、破損するおそれが考えられます。
LEDディスプレイとは異なり、液晶ディスプレイは破損個所が画面の一部であっても本体ごと交換しなくてはなりません。そのため従業員がデジタルサイネージを確認する際は腰道具に注意するなど、利用時の注意を促しましょう。
まとめ
工事現場にデジタルサイネージを設置することで、作業員の安全や健康に関する注意喚起や業務上の情報共有など、作業効率や安全性の向上につながります。
ただし、工事現場でデジタルサイネージを安全に活用するためには、設置場所にあった種類のディスプレイを選ぶことが重要です。
デジタルサイネージを工事現場で活用することで、工事業界のDX化への推進につながります。また紙の消費を減らすことで環境負荷の低減といったSDGsの目標達成なども期待できることから、今後はさらに工事現場へのデジタルサイネージの導入が進むと考えられています。
アイネットの初期費用&月額費用0円プランはこちらから!
参考: 建設業界の外国人材不足を解決!特定技能受け入れガイド【メリット・デメリット、事例】 | 外国人採用の窓口