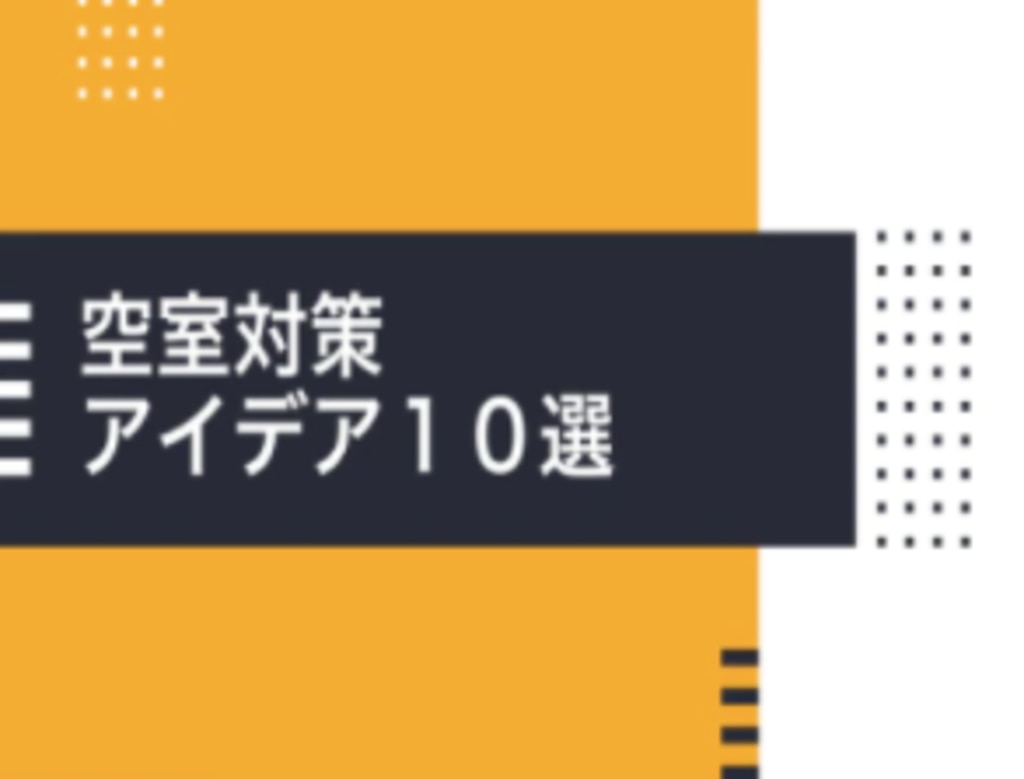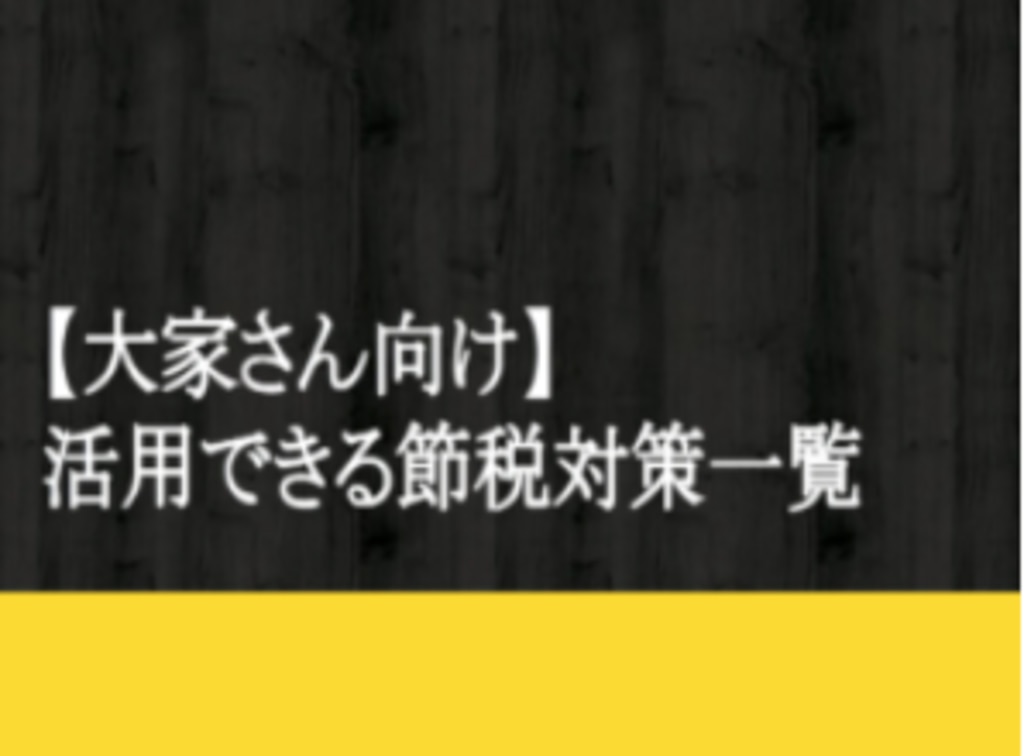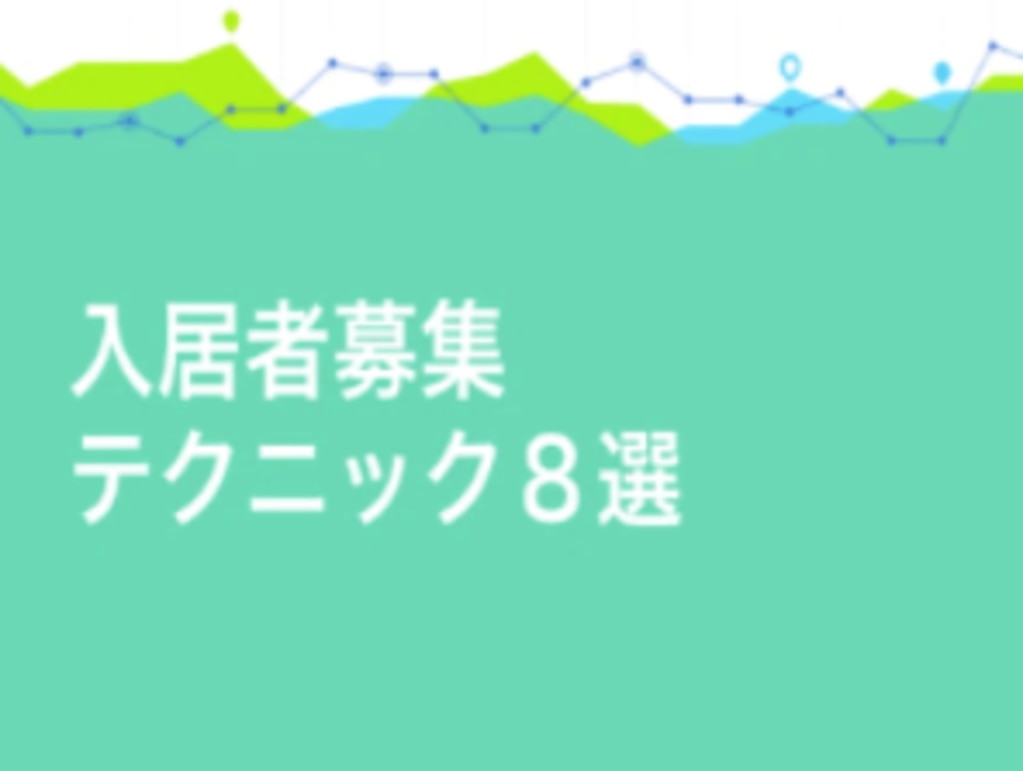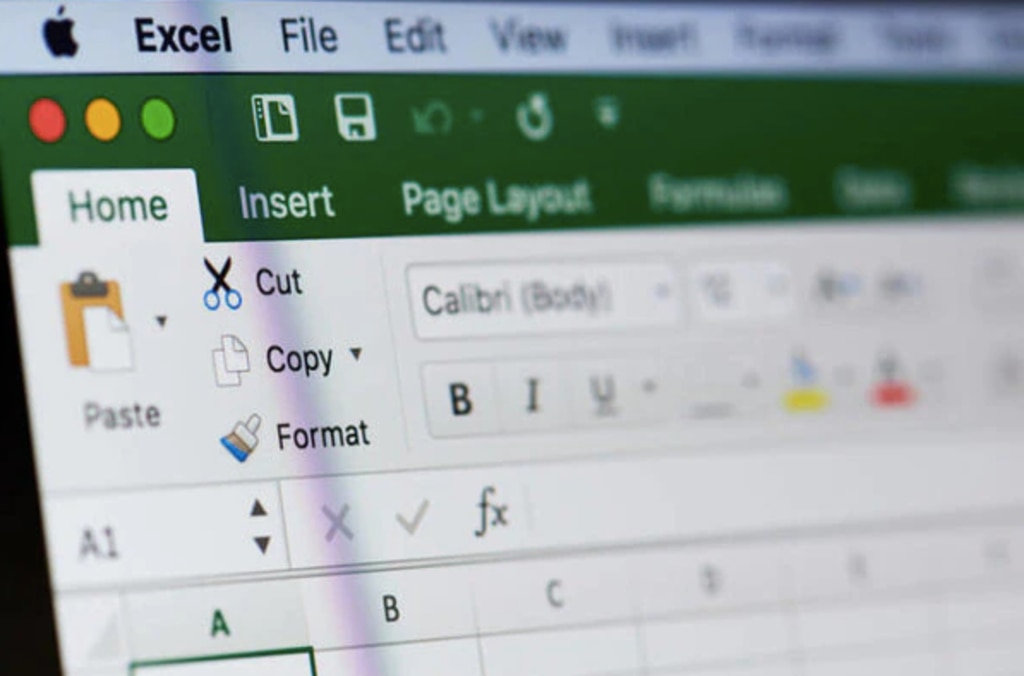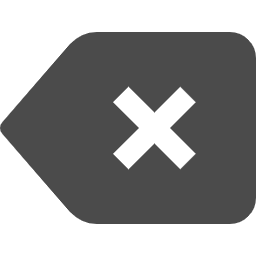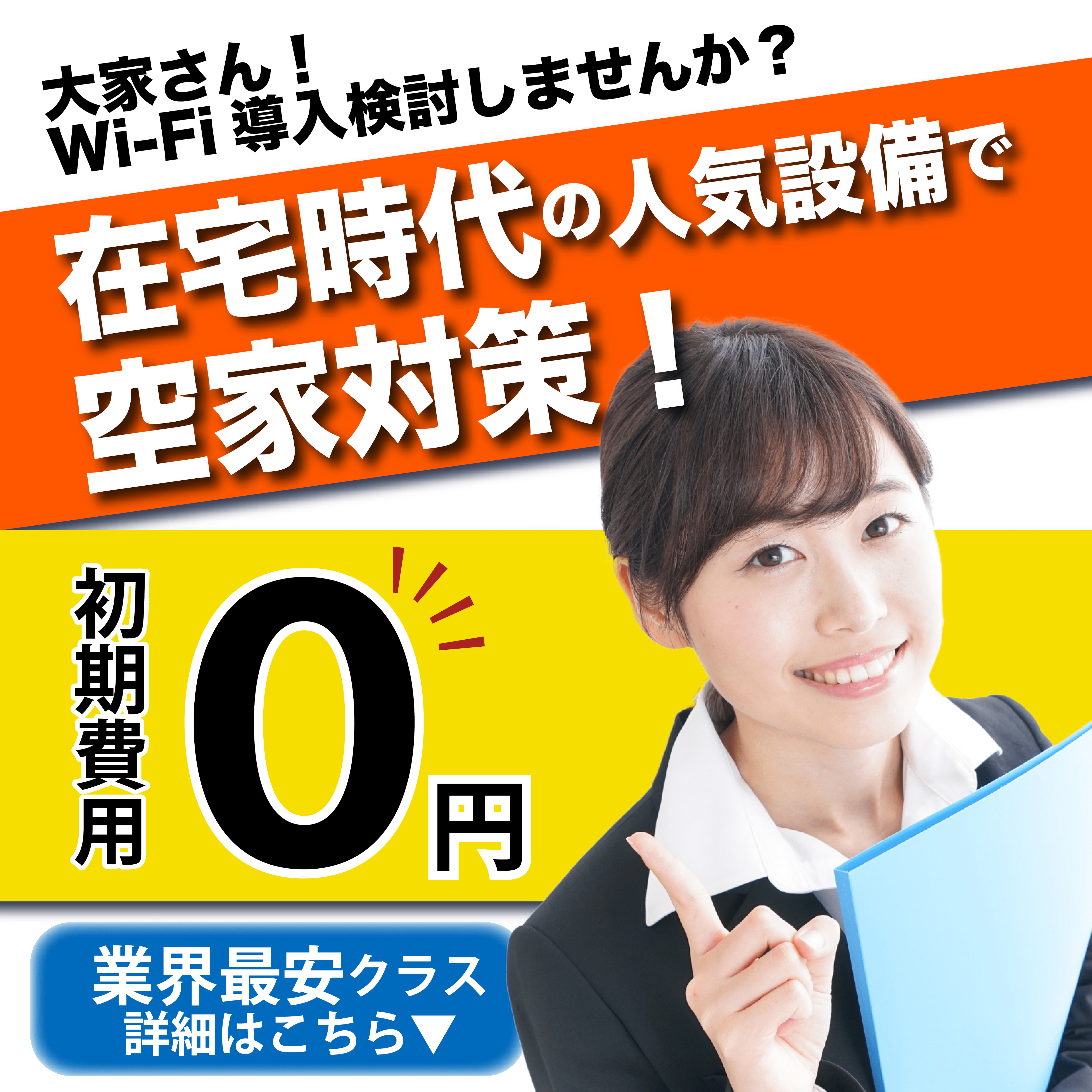【2025年最新版】太陽光発電の“発電量”を完全解説!1日・年間・地域別目安と効率を上げるコツ

「太陽光発電システムの発電容量の目安は?」
「太陽光パネルの発電効率を上げる方法を知りたい」
「太陽光発電で自宅の使用電気をまかなえる?」
太陽光発電について、こういった疑問を持つ人は少なくないでしょう。
そこで今回は、太陽光発電システムの発電量について、主に以下の内容を解説します。
- 発電容量別の発電量の目安
- 発電量に影響する要素
- 発電効率を最大化する方法
- 「見える化」の活用方法
- 地域別の日照時間と発電量
また、太陽光発電システムの発電量について「よくある質問」もまとめました。
これから太陽光発電システムの導入を検討中の方はもちろん、発電効率で悩んでいる方もぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.太陽光発電の「発電量」とは?基本のキ・換算式
- 2.1日・月・年間でどれくらい発電する?モデル別シミュレーション
- 3.太陽光発電量に影響する5大要素
- 3.1.① 方角・屋根勾配:電効率がよいのは南向き30°
- 3.2.② 地域差
- 3.3.③ 季節・天候
- 3.4.④ パネル性能・パネルの表面温度
- 3.5.⑤ 影・汚れ・配線ロスなど
- 3.5.1.太陽光パネルに影が差す場合
- 3.5.2.太陽光パネルの表面が汚れている場合
- 3.5.3.配線やパネルが劣化している場合
- 4.太陽光発電量を最大化する5つの施策
- 4.1.最適容量設計とレイアウト
- 4.2.高効率パネルと最新パワーコンディショナの採用
- 4.3.定期清掃・草刈り・点検でロス削減
- 4.4.蓄電池併設で自家消費率アップ
- 4.5.発電データのモニタリング&AI診断の活用
- 5.モニタリングと診断で発電量を「見える化」する方法
- 5.1.HEMS・クラウド監視・スマートメーター
- 5.2.目標発電量との比較チェックリスト
- 5.3.発電低下を早期発見する指標
- 6.地域別・方角別の日照時間と発電量目安
- 6.1.全国主要都市の年間日照時間と推定kWhの一覧表
- 6.2.東西日本・太平洋側/日本海側の傾向
- 6.3.積雪地域のシーズナルギャップ対策
- 7.経年劣化と長期発電量の見込み
- 7.1.パネル出力低下率(年0.25-0.5%)と対策
- 7.2.パワーコンディショナの交換タイミングと費用
- 7.3.長期保証の読み解き方
- 8.太陽光発電量と経済メリット―費用対効果を測る指標
- 8.1.発電量×電気代高騰シナリオで見るROI
- 8.2.売電と自家消費のベストミックス
- 8.3.自治体補助金と税制優遇で初期費用を圧縮
- 9.太陽光発電の発電量FAQ
- 10.まとめ
- 11.この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
太陽光発電の「発電量」とは?基本のキ・換算式

自宅や所有するアパートの屋根などに太陽光発電システムを設置する場合、まずどのくらいの電気を発電できるか把握しておきましょう。
ここでは、太陽光発電システムの発電量の目安と発電量を求める計算式を紹介します。
kWとkWhの違い/計算式〈発電量=容量×日射量×PR〉
まず、太陽光発電システムで発電した電気の量は「kWh」という単位で表します。
「kWh」を構成するアルファベットは、それぞれ以下の意味を示します。
- k(キロ):「1,000倍」のこと
- W(ワット):瞬間的な「電力」のこと
- h(アワー):「時間」のこと
1kWとは、「1,000W」のことです。
ようするに太陽光発電システムによる発電量は、瞬間的な電力「kW」に時間「h」をかけることで「発電量kWh(キロワットアワー)」と表されるのです。
太陽光発電システムの年間発電量は、次の式で求めることができます。
年間発電電力量EPY = PAN × HA × K × 365 (kWh/年)
計算式内の各記号の意味は以下のようになります。
- PAN:標準状態における太陽電池出力 (kW)(標準状態:AM1.5・日射強度 1000W/㎡・太陽電池セル温度 25℃)
- HA:設置場所での日射量 (kWh/㎡・日)
- K:総合設計係数(温度補正係数・回路損失・機器による損失等で通常は 0.7 程度)
参考:社団法人日本電機工業会『公共用・産業用太陽光発電システム計画ガイドブック 』
ただし、発電量は、場所・季節・年・設置条件などによって変動するため、上記で求めた数値は、あくまで推定発電量として参考値であることを留意しておきましょう。
住宅用の平均発電量は1 kWあたり年間1,000~1,200 kWh
太陽光発電システムによる年間発電量はシステムの容量によって異なりますが、平均は容量1kWあたり1000kWh/年~1200kWh/年程度となります。
目安としてシステム容量1kWあたり「約1,100kWh/年」と考えておくとよいでしょう。
1日・月・年間でどれくらい発電する?モデル別シミュレーション

太陽光発電システムの発電量は、システムの容量によって異なります。
ここでは、容量3 kW~6 kWの太陽光発電システムによる発電量・売電集収入の違いについて解説します。
3~6 kWシステムの年間発電量&売電収入早見表
下記は、太陽光発電システムの容量を3kW~6kW変化させたときの発電量と年間売電収入を一覧表にしたものです。
太陽光発電システムの1kWあたりの発電量を1,100kWh/年(年間発電量の目安)、売電収入はFITによる売電単価15円/kWh(2025年度の単価)、自家消費率30%として計算しました。
設置容量 |
1日の発電量(kWh) |
1ヶ月間の発電量(kWh) |
1年間の発電量(kWh) |
年間売電収入 |
|---|---|---|---|---|
3kW |
約9.2 |
275.0 |
約3,300kWh |
34,650円 |
4kW |
約12.2 |
約36.6 |
約4,400kWh |
46,200円 |
5kW |
約15.2 |
約458.3 |
約5,500kWh |
57,750円 |
6kW |
約18.3 |
550.0 |
約6,600kWh |
69,300円 |
このように太陽光発電システムの容量を大きくすれば、それだけ年間発電量が増え、年間売電収入も増加します。
ただし、屋根の広さや形状などによって、設置できる太陽光発電システムの容量が決まります。
なお、上記の発電量はあくまでも目安の数値です。
前述したように、太陽光発電システムの発電量は、場所・季節・年・設置条件などによって変動します。
また買電収入は自家消費率によっても変わることを念頭においておきましょう。
1日あたりの発電量の全国平均
住宅用太陽光発電システムは、一般的に容量10kW未満です。そのうち多く選ばれるのが容量3kW〜6kWのシステムです。
そのため、年間発電量の目安を1,100 kWhとした場合、1kWの 1日あたりの発電量は約3.1kWhとなります。
太陽光発電システムの設置を検討する際の目安としておぼえておきましょう。
太陽光発電量に影響する5大要素

太陽光発電システムの発電量はさまざまな要素によって変動します。
発電量に影響するのは、おもに以下の要素があります。
- 方角・屋根勾配
- 地域差
- 季節・天候
- 温度・パネル性能
- 影・汚れ・配線ロスなど
それぞれについて詳しく解説します。
① 方角・屋根勾配:電効率がよいのは南向き30°
太陽光発電システムの発電量は、屋根の向きや設置角度が影響します。
もっとも発電効率がよいのは「南向きで設置角度30°」です。
上記以外の方角・設置角度でも発電は可能ですが、発電量は少なくなるのが一般的です。
なお、屋根の形状によっては、太陽光発電システムの設置がむずかしい場合もあります。
まずは専門業者に、太陽光発電システムの設置に適しているかどうか確認してもらいましょう。
② 地域差
太陽光発電システムの発電量は日照時間に大きく左右されます。そのため、地域差が日照時間に大きく影響します。
年間を通して日照時間の長い地域ほど発電量も多くなりますが、一方で日照時間が短い地域は発電量が少ないです。
下記は気象庁のデータ(1991年~2020年の平年値)から、日照時間がもっとも長かったのは山梨県でした。一方で日照時間がもっとも短かったのは秋田県であることがわかりました。
参考:気象庁『各種データ・資料 日照時間一覧表』
ただし、日照時間は毎年の天候が大きく影響します。
太陽光発電の発電量に天候が影響する件について、次項をご覧ください。
太陽光発電システムを導入する際は、お住まいの都道府県・市区町村ごとの日照時間や発電量などを確認するとよいでしょう。
③ 季節・天候
太陽光発電システムの発電量は日照時間に大きく左右されます。特に季節と天候は日照時間と密接にかかわるため見逃せません。
一般的に夏は日照時間が長く太陽の高度が高いため、太陽光発電システムによる発電量が多くなります。
ただし、夏であっても気温が高すぎると発電効率は悪化する傾向が強いです。
一方で冬は日照時間が短く、太陽の高度も低くなるため発電量は減少します。
また積雪の多い地域では、太陽光パネルに雪が積もってしまうと発電量が減少しやすくなります。
また日照時間は天候によって大きく異なります。梅雨や台風、積雪などが日照時間に大きく影響するためです。
そのため同じ地域であっても、その年の天候次第で日照時間が短くなり、太陽光発電システムの発電量が減少する可能性があるのです。
以上の点から日本では4月〜5月の発電量がもっとも多くなりやすいと考えられます。
④ パネル性能・パネルの表面温度
太陽光発電システムの発電量は、設置した太陽光パネルの性能によって大きく左右されます。
同じ枚数の太陽光パネルを設置しても、メーカーや種類によって発電量が異なります。
1枚あたりの年間発電効率が高いパネルを選べば、かぎられた設置面積でも、より多くの電気を発電できるのです。
太陽光パネルの年間発電量は「モジュール変換効率」によって異なります。
モジュール変換効率とは、太陽光パネルの1㎡あたりの変換効率のことです。
たとえば、「京セラ」の太陽光パネル(縦1.7m×横1.1m=約1.95㎡)のモジュール変換効率は210W/㎡となります。
1kW あたりの年間発電量が1,100kWhとすると、この京セラの太陽光パネル(210W/㎡)1㎡あたりの年間発電量は210kWhとなります。
ただし、太陽光パネルの年間発電量は設置条件によっても左右されます。
特に気温が高くなると太陽光パネル表面温度が上昇し、発電効率が低下するため注意が必要です。
またパネルの経年劣化によっても発電効率は低下します。
太陽光パネルの寿命は、メーカーや種類によって異なりますが、長寿命タイプのパネルを選ぶことで長期の発電に耐えることができるでしょう。
⑤ 影・汚れ・配線ロスなど
太陽光発電システムの発電量は、設置場所やメンテナンスによって変動する可能性があります。
次のケースでは、太陽光発電システムの発電量が減少する場合が考えられます。
太陽光パネルに影が差す場合
太陽光発電システムは発電するために日光が必要です。そのため、システムに影がかかる場合は発電量が減少してしまいます。
影を作る物体としては、建物・煙突・樹木など、さまざまな要因が考えられます。
太陽光発電システムを導入する際は、時間を変えて現地を確認し、影ができないことを確認したうえで設置することが大事です。
太陽光パネルの表面が汚れている場合
太陽光発電システムは屋外に設置するため、砂埃・鳥の糞・落ち葉などの汚れが太陽光パネルの表面に付着すると発電量が減少する原因となります。
パネル表面を定期的に清掃することで安定した発電量を維持することができます。
配線やパネルが劣化している場合
太陽光パネルや配線の劣化が原因で発電量が減少するケースもあります。
一般的な太陽光パネルは長期使用に耐えられるように設計されていますが、経年とともに劣化します。
メーカーにもよりますが、パネルの発電出力保証は10年~25年としているケースが多いです。そのため保証期間が終了した直後に発電量が低下するケースが見られます。
経年劣化によって発電量が低下した太陽光パネルは修理などができないため、新しいパネルと交換しなくてはなりません。
長期にわたって太陽光発電システムの発電量を維持したい場合は、寿命が30年以上のパネルを選ぶことをおすすめします。
また、台風・大雪・飛来物などによって配線やパネルが破損や故障し、太陽光発電システムの発電量が低下する場合もあります。
破損や故障などの防止・早期対応をおこなうためにも、定期的にメンテナンスをおこないましょう。
太陽光発電量を最大化する5つの施策

ここでは太陽光発電システムの発電効率を最大化するための方法を5つ紹介します。
最適容量設計とレイアウト
住宅用太陽光発電システムの最適容量を決める際は、家族構成や家屋のタイプなどを考慮したうえで検討しましょう。
住宅用太陽光発電システムの容量は、導入先の家族構成で選ばれるケースが多いです。
発電した電気の自家消費率にもよって異なりますが、自家消費予定の電気量に余裕を持たせた容量がおすすめです。
その結果、一般的な3人家族の場合は3 kW~4kWの太陽光発電システムが、電気の使用量が多い大家族は6 kW~8kWのシステムが最適容量と言われています。
また、近年増えている「オール電化住宅」に向けては7 kW~10kW未満の大容量設計がおすすめです。
また太陽光発電システムの設置個所にも注意が必要です。
太陽光発電システムは容量によって設置面積が決まります。またシステム容量が大きくなると重量も重くなるため、屋根の耐荷重性能の確認も必要です。
特に建物が古い場合、太陽光発電システムの荷重に耐えられない可能性があるため注意しましょう。
太陽光パネルの向きや角度などに留意し、できるだけ多くの日光が当たるようなレイアウトにするとよいでしょう。
なお、売電収入目的で太陽光発電システムを設置する場合、10kW以上の容量を選ぶことも可能です。
ただしその場合は産業用となるため、住宅用とは電気の買取単価が変わることを覚えておきましょう。
高効率パネルと最新パワーコンディショナの採用
前述したように太陽光発電システムの発電量は、太陽光パネルの性能によって大きく変動します。またパネルの損傷や経年劣化による発電効率の減少は避けられません。
そのため、長期にわたって最大の発電量を維持するためには、高効率かつ屋外で長期使用に耐えることができる長寿命タイプの太陽光パネルを選びましょう。
また、太陽光発電システムの発電量を維持するためには、太陽光パネル以外の設備にも留意が必要です。
たとえば太陽光発電システムを導入してから10年程度しか経っていないにもかかわらず、発電量が低下している場合は「パワーコンディショナ(PCS)」などの不具合が疑われます。
加えて、電圧上昇抑制がはたらくとパワーコンディショナの発電を抑え機能により、発電量が減少するケースがあります。
このように太陽光パネル事態に問題がないのにもかかわらず発電量が低下している場合は、早急にメンテナンスをおこない、必要に応じて最新のパワーコンディショナに交換するなどの対策をおこないましょう
定期清掃・草刈り・点検でロス削減
発電損失を最小に抑えることで、太陽光発電システムの発電量を維持できます。
太陽光パネルの破損や汚損による発電効率の低下を防ぐために定期的なメンテナンスや清掃をおこなったり、太陽光パネルに影がかからないように樹木の剪定・草刈り(地上置きの場合)をしたりしましょう。
蓄電池併設で自家消費率アップ
太陽光発電システムに蓄電池を併用することで、発電した最大量の電気を無駄なく使用できます。
たとえば、日中に発電した電気を夜間や電気料金の高い時間帯に自家消費することで電力会社から購入する電気量が減り、高い節電効果が期待できます。
また蓄電池があれば、災害などで停電が発生した場合でも電気を使用できるので安心感につながるでしょう。
発電データのモニタリング&AI診断の活用
太陽光発電システムの発電量をモニタリングすることで、発電状況を把握できるとともに効率的な運用が可能になります。
一般的なモニタリングシステムでは以下の内容が表示されます。
- 発電量
- 消費電力量
- 売電量
これらの数字をリアルタイムで確認できるため、発電量が低下するなど異常があってもすぐに対応できます。
またグラフやレポートなどで詳細なデータ分析や、遠隔監視でどこからでも確認できるなどのメリットがあります。
また近年増えてきているのが、ドローンを利用したAI診断です。
これまでは、太陽光発電システムのメンテナンスはパネルすべてを目視でおこなっていたため作業員の負担が大きく、またコストもかかりました。
AI診断は、ドローンで太陽光パネルを撮影し、その画像や動画をAI(人工知能)技術を利用したシステムで解析することで不具合を発見できます。
加えてドローンで撮影した動画と画像を保存しておくことで、2回目以降に撮影した画像と比較し、パネルの経年変化を確認することも可能です。
このようにモニタリングやAI診断を活用することで、業務の効率化およびコストの削減につながります。
モニタリングと診断で発電量を「見える化」する方法

太陽光発電システムの発電量などを「見える化」することで、発電効率や節電の効果を把握し、発電量の減少などの異常を発見しやすくなる効果が期待できます。
ここでは太陽光発電システムに関する電気を「見える化」するための方法について解説します。
HEMS・クラウド監視・スマートメーター
太陽光発電システムの発電量や電気の使用料などを「見える化」するには、以下のシステムや機器が役立ちます。
- HEMS
- クラウド監視
- スマートメーター
それぞれの役割りや特徴などを紹介します。
HEMS(ヘムス)
HEMS(ヘムス)とは、「Home Energy Management System」略称で、家庭で消費するエネルギーを「見える化」できるシステムのことです。
HEMSには以下の機能があります。
- 電気の使用量や太陽光発電システムの発電量・売電量を表示する
- 太陽光発電システムで発電した電気を最適なタイミングで振り分ける(蓄電池に充電する、直接消費するなど)
- スマートホーム化によって家電製品を自動制御できる(オン・オフ機能、最適な運転モードの選択など)
HEMSによって電力使用量を「見える化」することで省エネへの意識が高まり、その結果節電効果のアップが期待できます。
HEMSを導入することで、電気の使用量はもちろん、太陽光発電システムによる発電量・売電量の把握が容易におこなえます。
また「スマートHEMS(またはHEMS対応家電)」なら、発電した電気の蓄電池への振り分けや家電品の消費電力を自動で制御することが可能になるため、高い節電効果がえられるでしょう。
クラウド監視
クラウド監視は、HEMSで取得した発電量・売電量、消費電力などのデータをクラウド上に保存・分析し、その結果をインターネット経由で確認できるシステムです。
スマートメーター
スマートメーターは、従来の電気の使用量(買電した電気の量)メーターと太陽光発電システムで発電した電気の売電量を計測できる計量器のことです。
利用者は1台のメーターで買電量と売電量の確認ができ、そのデータは自動的に電力会社に送信されるため検針不要なのが特徴です。
スマートメーターとHEMSはそれぞれ単独でも利用できますが、連動させることで家庭内の電力使用状況をより詳しく把握できます。
目標発電量との比較チェックリスト
HEMSやスマートメーターなどで電力量の動きを「見える化」することで、日次・月次ごとのデータと過去のデータを簡単に比較できるようになります。
また太陽光発電システムの目標発電量と実際の売電量の差異なども把握しやすくなります。
発電低下を早期発見する指標
「見える化」することで、太陽光発電システムによる発電量の詳細を確認できます。
たとえば、発電量の低下などの異常を早期に発見することも可能です。
早い段階で修理をおこなうことで、損失を最小に抑えることにつながります。
地域別・方角別の日照時間と発電量目安

ここでは国内の地域別の日照時間・発電量の目安を紹介します。
全国主要都市の年間日照時間と推定kWhの一覧表
ここでは日照時間の多い3都市と少ない3都市について、日照時間(年間平均)と年間予想発電量を一覧表で紹介します。
【日照時間の多い3都市】
都市 |
平均日照時間/年 |
年間予想発電量(kWh/年・kW) |
|---|---|---|
甲府市 |
2,225 |
1,522 |
前橋市 |
2,153 |
1,441 |
静岡市 |
2,123 |
1,431 |
【日照時間少ない3都市】
都市 |
平均日照時間/年 |
年間予想発電量(kWh/年・kW) |
|---|---|---|
秋田市 |
1,527 |
1,108 |
青森市 |
1,589 |
1,140 |
新潟市 |
1,639 |
1,162 |
全国で日照時間が1番多いのは山梨県甲府市でした。一方で1番少ないのは秋田県秋田市で、甲府市と比べると日照時間は約700時間・発電量は約410 kWh少ないことがわかりました。
なお、同じ地域内でも地形や方角・周辺環境などによって日射時間や日照量は左右されます。
太陽光発電システムの導入を検討する際は、都道府県・市区町村ごとの日照時間や発電量などをかならず確認しましょう。
参考:気象庁『各種データ・資料 過去の気象データ』
参考:環境省『令和3年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書』
東西日本・太平洋側/日本海側の傾向
日照時間の多い都道府県は、主に山梨県甲府市のように内陸の地域、静岡県静岡市など太平洋側の地域です。平均して、台風や梅雨の影響が少ない・降雪量の少ない地域が該当します。
これらの都市は発電量も多く、太陽光発電に向いている地域と言えるでしょう。
一方、日照時間が少ないのは、秋田県秋田市や青森県青森市など、北側で日本海に面した地域が多くなります。これらの都市は発電も少ない傾向が強いです。
このように日照時間と発電量は密接に関係しますが、日照時間が多いすべての地域で発電量が多いかというとそうではありません。
日照時間が長くても気温が高い地域では発電効率が低下してしまうため、一概に日照時間だけで発電量の多寡を判断するのはむずかしいと考えられます。
積雪地域のシーズナルギャップ対策
積雪のある地域で太陽光発電システムを設置する場合はシーズナルギャップ(季節による発電量の変動)対策が欠かせません。
主なシーズナルギャップ対策は、以下のような方法があります。
- 蓄電池を併設する:発電量が少ない冬場で充電した電気を使用し、同時に電力会社と契約することで、安定した電力の供給を確保する
- 発電量の予測:あらかじめ発電量を予測したうえで使用量を調整し、安定した電力供給を図る
また、シーズナルギャップ対策と同時に積雪対策をおこなうことで、冬期の発電効率を上昇させることが可能です。
主な積雪対策には次のような方法があります。
- 太陽光パネルの設置角度を調整して、パネル上の雪が自然に滑り落ちやすくする
- 融雪装置を設置し、雪を溶かすことで発電量を増加させる
- 専門業者に雪下ろしを依頼する
そのほかにも、積雪の重さに耐えられるよう、架台の強度を上げたり、耐荷重の高いパネルを導入したりしましょう。
経年劣化と長期発電量の見込み

ここでは太陽光発電システムの経年劣化による発電量の低下時の対策方法や、長期に渡って発電する場合の注意点について解説します。
パネル出力低下率(年0.25-0.5%)と対策
太陽光発電システムの発電量は、経年によって年間で0.25%~0.5%程度低下するのが一般的です。
パネルの経年劣化による対策方法としては、定期的なメンテナンスやパネルの清掃を置こうなとよいでしょう。
その際は、パネルだけなく架台や配線などにも損傷や劣化がないか確認すると、より効果的です。
また必要に応じてパワーコンディショナの交換もおこないましょう。
パワーコンディショナの交換タイミングと費用
太陽光発電システムのパワーコンディショナの寿命は10年~15年程度とされています。
そのため、太陽光発電システムの設置から10年を過ぎたあたりで発電量が低下した場合は、パワーコンディショナの寿命が疑われます。
ただし、10年未満であっても発電量が低下した場合は、パワーコンディショナが故障した可能性もあるため、早めに専門業者に点検を依頼しましょう。
パワーコンディショナの交換費用の目安は30万円~40万円程度ですが、メーカーによって異なります。なお故障の場合、保証期間内であれば無償・割引価格で交換できる場合もあります。
長期保証の読み解き方
太陽発電システムの太陽パネルや周辺機に対して、ほとんどのメーカーが保証期間を設けています。
保証期間は機器によって異なりますが、パワーコンディショナを含む周辺機器などは10年~15年程度、太陽光パネルには10年~25年程度のメーカー保証を提供している場合が多いです。
このように保証期間はメーカーや機器の種類によって異なるため、導入の際にはかならず確認しましょう。
ただし、保証期間内であってもすべての製品が保証される訳ではないため注意が必要です。
メーカーや製品にもよりますが多くの場合、保証される不具合の範囲や条件などが設定されています。
たとえば、自然災害や取り扱いの不備による故障は保証対象外となるケースが多いようです。
また太陽光パネルの「出力保証」の下限値は初年度の発電出力を基準とし、経年によって一定の割合で下限値が設定されるのが一般的です。
ただし初年度の基準値は100%だったり、97%だったり、メーカーによって異なります。
太陽光パネルの保証についても、ほかの周辺機器同様、保証を受けるための条件が設定されている場合が多いです。
メーカーによって違いはありますが、多くの場合で以下のような条件が設定されています。
【太陽光パネルの出力保証の主な条件(例)】
- パネルの設置角度・方角・設置場所(日照条件)などが適切であること
- 定期的な清掃やメンテナンスが適切におこなわれていること
- 積雪や落下物によって過度な損傷を受けていないこと
上記に該当しない場合は保証を受けられない場合もあるため注意が必要です。
太陽光パネルを選ぶ際は価格だけでなく、出力保証の内容や条件などもしっかりと確認することをおすすめします。
太陽光発電量と経済メリット―費用対効果を測る指標

ここでは、太陽光発電システムに関するROIや補助金制度について紹介します。
発電量×電気代高騰シナリオで見るROI
ROI(Return on Investment)とは、投資した金額に対して利益率や投資回収期間などを判断する際に使用する指標です。
太陽光発電システムのROIを求める計算式は以下のようになります。
【ROIの計算式】
設置費用 ÷(年間の売電収入+電気代の削減額)= ROI(投資回収年数)
ここでは、電気料金が上昇した際のROI(投資回収年収)の変化を「3kW(発電量3,300 kWh)の住宅用太陽光発電システム」を例に計算してみました。
なお、自家消費率30%(990kWh)・売電単価15円/kWh・基本の電気料金31円/kWh・設置費用(投資額)90万円で計算します。
【基本のROI(投資回収年数)】
設置費用90万円 ÷(年間の売電収入34,650円+電気代の削減額30,690円)
=ROI(投資回収年数)約13.7年
基本の電気料金が31円/kWhの場合、設置費用90万円を回収するには約13.7年かかることがわかりました。
では、電気料金が高騰した場合、ROIの変化について見てみましょう。
【電気料金が年2%上昇(31.6円/kWh)標準的な上昇シナリオの場合】
設置費用90万円 ÷(年間の売電収入34,650円+電気代の削減額31,284円)
=ROI(投資回収年数)約13.6年
電気料金が年2%上昇すると投資回収年数は約13.6年となり、基本の回収年数より約1ヶ月短縮されます。
【電気料金が年5%上昇(32.6円/kWh)高インフレシナリオの場合】
設置費用90万円 ÷(年間の売電収入34,650円+電気代の削減額32,274円)
=ROI(投資回収年数)約13.4年
電気料金が年5%上昇すると投資回収年数は約13.4年となり、基本の回収年数より約3ヶ月短縮されます。
このように電気料金が上昇することで自家消費する電気量の節電額が多くなり、その結果、回収期間の短縮につながります。
ただし、上記のROIの計算にはランニングコスト(メンテナンス費用など)が反映されていません。そのため、あくまでシミュレーションとして数字は参考程度に留めてください。
売電と自家消費のベストミックス
太陽光発電システムにおける売電と自家消費の割合の目安は、売電率70%程度、自家消費率30%程度が一般的です。
ただし、家族構成や蓄電池の設置の有無によって、自家消費の割合を増やすことも可能です。
以前と比較して現在は太陽光発電による売電価格が下落しているため、売電による収入は減少しています。
一方で電力料金の高騰によって、売電するよりも自家消費量を増やすことで電気料金を削減したほうが得になる傾向があります。
できるだけ発電した電力を自家消費して電気代を節約したい場合は、蓄電池を併用するのがおすすめです。
蓄電池に日中に発電した電力を貯めておき、夜間や早朝、電気料金の高い時間帯に使用することで大幅な電気代の削減につながるでしょう。
自治体補助金と税制優遇で初期費用を圧縮
太陽光発電システムの初期費用(設置費用)を削減するためには、各自治体が提供している補助金制度や税制優遇などを上手に利用するとよいでしょう。
たとえば東京都では、太陽光発電・家庭用蓄電池・V2Hの設置に対して、それぞれ100万円以上の補助金が交付されています。
太陽光発電システムや周辺機器に関する補助金の交付は、自治体によって異なります。
また予算・対象となる要件・申請スケジュールなどは補助金の種類によって異なるため、かならず利用できるわけではありません。
太陽光発電システムに関する補助金を利用したい場合は、お住まいの自治体窓口やホームページで確認しましょう。
なお、住宅用太陽光発電システムの導入に対する国からの補助金制度はありません。ただし法人向け太陽光発電に対しては補助金制度が設けられています。
太陽光発電の発電量FAQ

ここでは太陽光発電システムの発電量に関するよくある質問をまとめました。
Q:曇りや雨の日の発電量はどうなりますか?
A:太陽光発電システムは、曇りや雨の日でも発電します。ただし、晴天時と比べて発電量は少なくなります。目安としては、曇りの日は晴天時の3分の1~10分の1程度、雨の日は5分の1~20分の1程度に低下します。
Q:雪で太陽光パネルが覆われるとどうなりますか?
A:積雪量によって太陽光発電システムの発電量が低下します。パネル全体が雪で覆われてしまうと発電ができなくなるため注意が必要です。
積雪対策として、パネルの角度を設定して雪がすべり落ちやすくしたり、専門業者に雪下ろしを依頼したりするとよいでしょう。
Q:増設/容量変更はできますか?
A:太陽光発電システムの設備の増設や容量変更は可能ですが、手続きなどが必要になるケースがあります。
特にFITの認定を受けている場合は「変更認定申請」が必要になります。また増設後の容量によっては売電価格や買取期間が変わる場合もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
まとめ
太陽光発電システムの発電量は、さまざまな要因によって変動します。
そのため、太陽光発電システムを導入する際は、日照時間や日射量だけでなく、地域差や太陽光パネルの性能などによって発電量が左右されることに留意しておくことが、太陽光発電を最大化する際に役立ちます。
ぜひ当記事を参考にして、太陽光発電システムによる発電量の最大化を維持してください。
この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
>>アパート経営シミュレーション無料エクセルソフト5選
>>カテゴリー別おすすめアパート建築会社一覧
>>大家さん必見の空室対策アイデア10選
>>アパートWiFi導入のメリット&デメリット
>>入居者募集テクニック8選