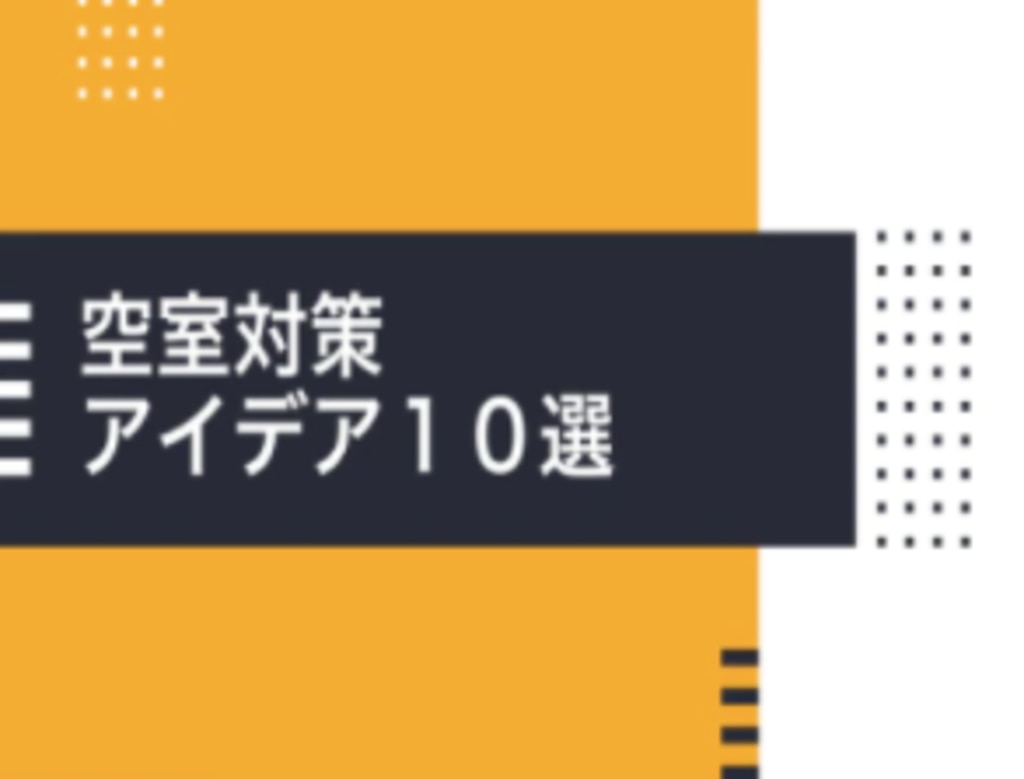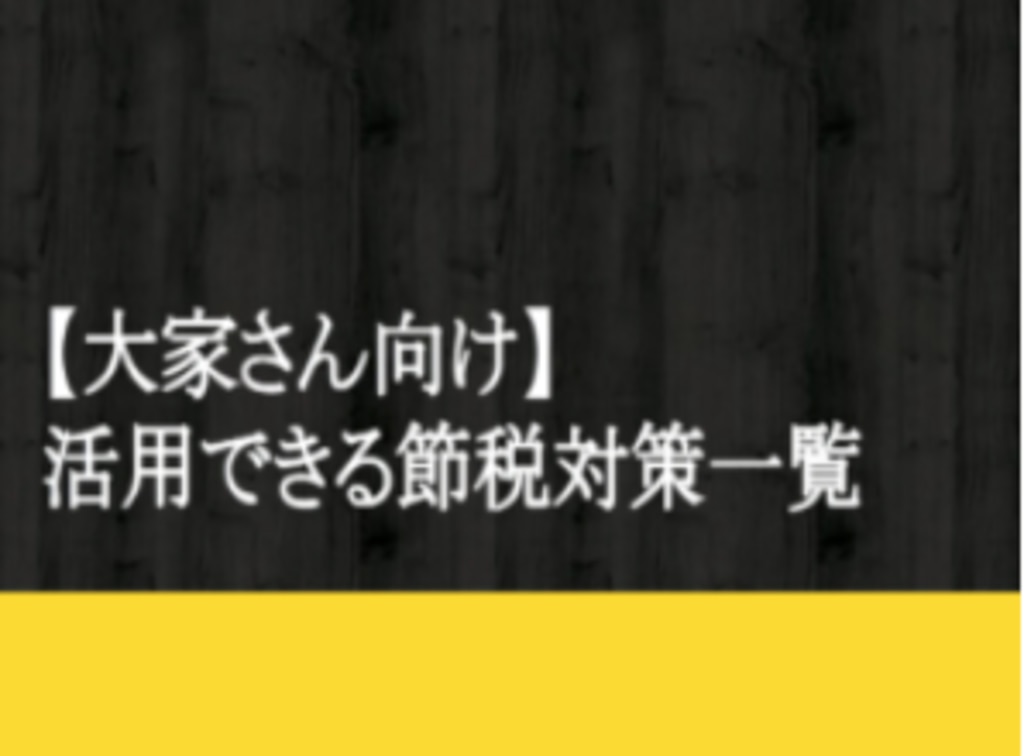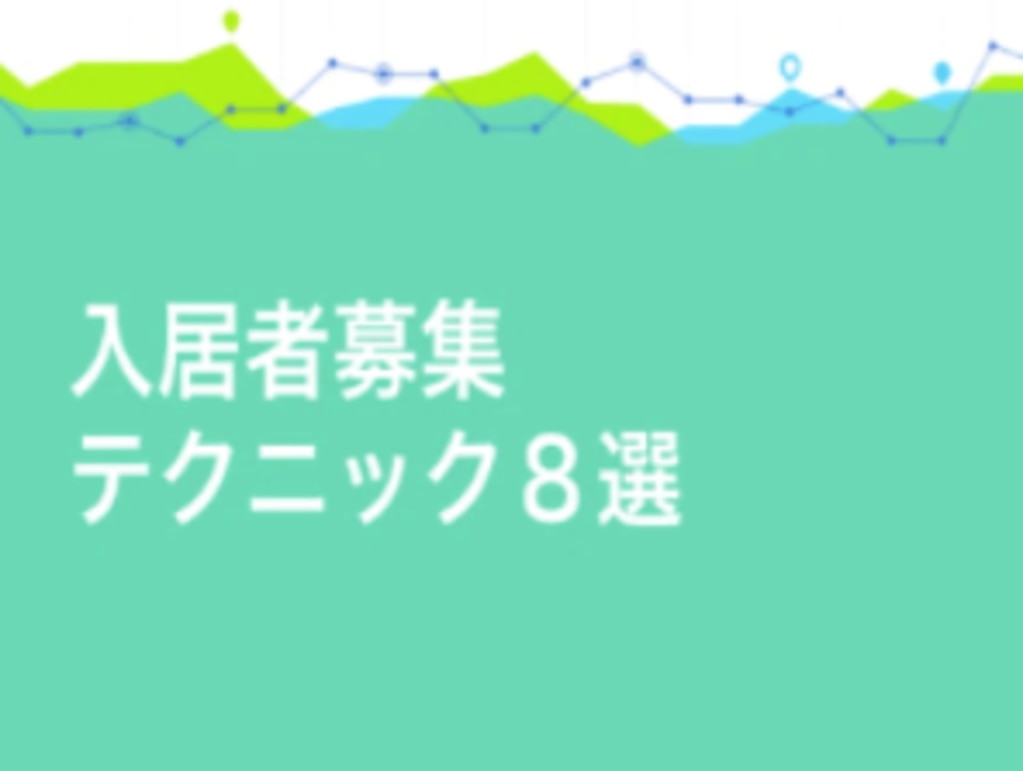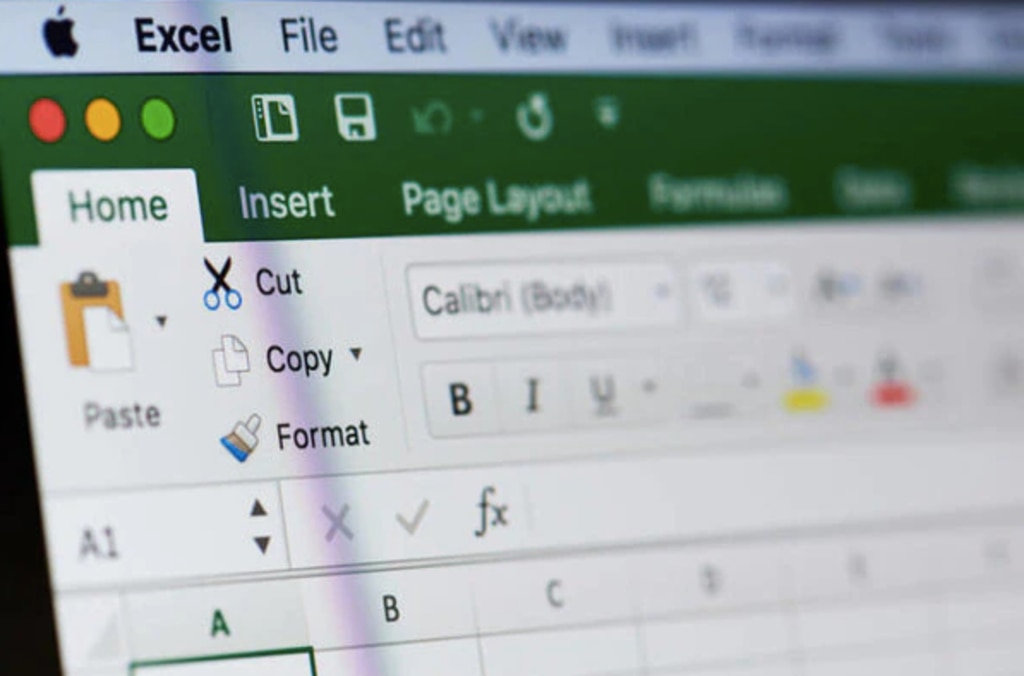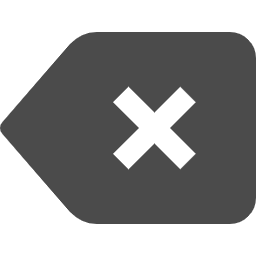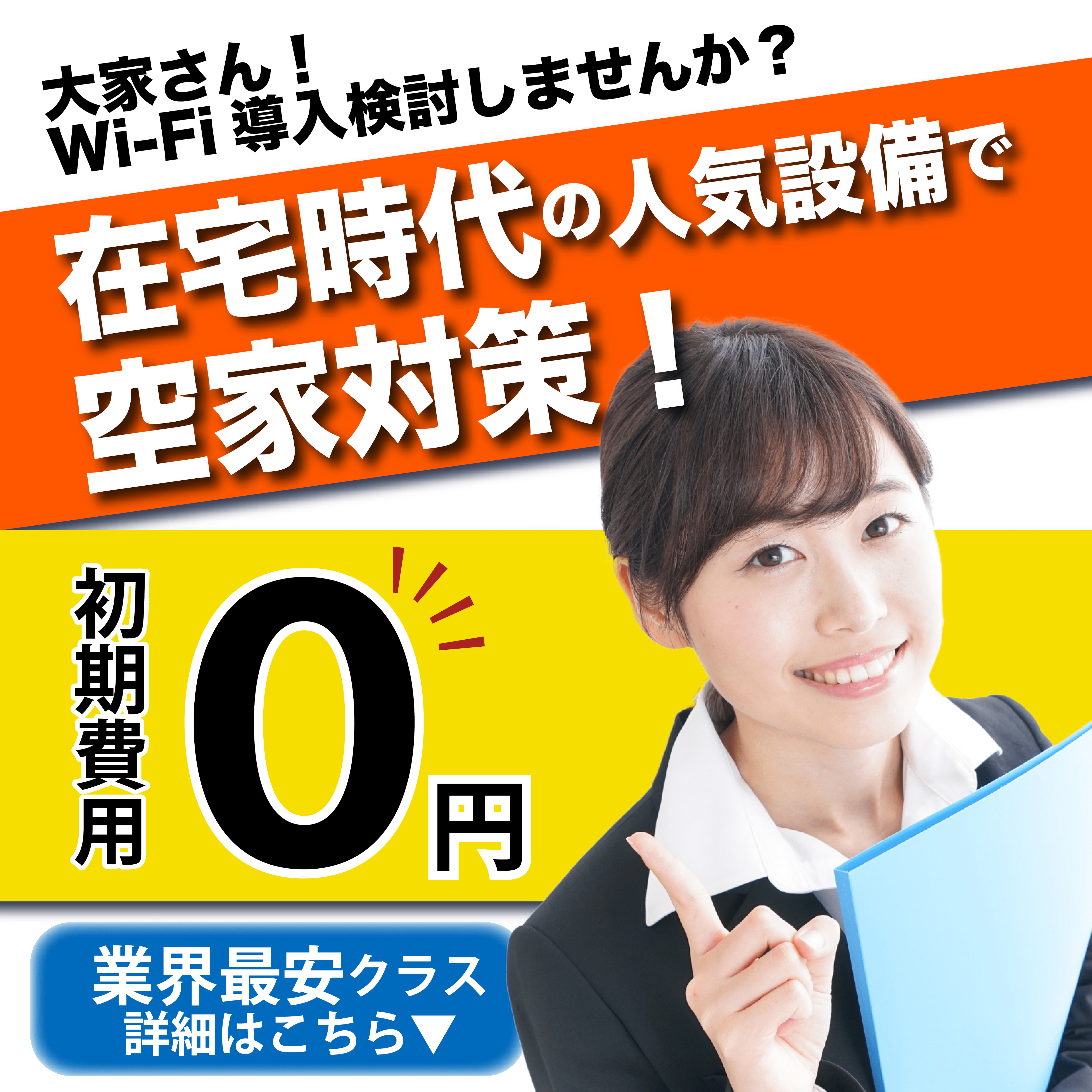【2025年最新】太陽光発電の売電を解説!買取価格・手続き・卒FIT後まで丸わかり

電気料金が高騰する昨今、自宅や所有するアパートなどに太陽光発電システムの設置を検討する人が増えています。
しかし、太陽光発電を導入するにあたって、わからない点がたくさんあるという人も多いでしょう。
「太陽光発電の買取価格はいくら?」
「太陽光発電で売電するための手順は?」
「卒FIT後はどんな選択肢があるの?」
今回は太陽光発電システムについて、2025年度最新の売電価格を紹介します。
またこれまでの売電価格の推移と共に今後の見通しや、卒FIT後の選択肢などについても解説します。
目次[非表示]
- 1.2025年度の売電制度(FIT/FIP)の最新概要
- 2.売電価格の推移と今後の動向
- 3.売電収入シミュレーション【戸建て4 kW/産業用10 kW】
- 3.1.年間発電量×買取単価で見る収益モデル
- 3.1.1.4kWの住宅用太陽光発電システムの場合
- 3.1.2.10 kW産業用太陽光発電システムの場合
- 3.2.電気料金高騰シナリオ別のROI比較
- 3.3.蓄電池併設で収益がどう変わるか
- 4.太陽光発電の売電を始めるための手続きフロー
- 4.1.売電を始める際の手続き
- 4.1.1.① 設備認定(JPEA)を受ける
- 4.1.2.② 系統連系契約
- 4.1.3.③ 施工・検査
- 4.1.4.④ 売電開始
- 4.2.必要書類と平均スケジュール
- 4.2.1.事業計画認定申請・認定に必要な期間と書類
- 4.2.2.系統連系契約申請に必要な期間と書類
- 4.3.計量器(スマートメーター)の設置と読み取り方法
- 4.3.1.スマートメーターの見方
- 5.卒FIT後の3つ選択肢
- 6.太陽光発電の売電収入を最大化するコツ
- 7.太陽光発電の売電時によくあるトラブルと対策
- 8.太陽光売電で活用できる補助金・優遇策(2025年度版)
- 8.1.国の再エネ導入促進補助(太陽光+蓄電)
- 8.2.自治体の上乗せ補助・利子補給
- 8.3.固定資産税1/2軽減など税制優遇
- 9.太陽光発電の売電に関するよくある質問(FAQ)
- 9.1.Q:売電収入にかかる税金は?
- 9.2.Q:途中でFIPに移行できる?
- 9.3.Q:屋根修繕が必要になった場合の対応は?
- 10.まとめ
- 11.この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
2025年度の売電制度(FIT/FIP)の最新概要

ここでは22025年度の太陽光発電による売電制度について、最新の買取価格を紹介します。
FITとFIPの仕組みと違い
FITとは、「Feed-in Tariff」の略で、再生可能エネルギー(再エネ)で発電した電気を電力会社が一定期間・固定価格で買い取る制度のことです。
一方、FIPは「Feed-in Premium」の略で、再エネの売電価格は時期や時間帯により市場価格に一定のプレミアム(補助額)が上乗せされて支払われる仕組みです。
そのほかにも両者は、インバランス負担や非化石価値などが異なります。
【FITとFIPの違い】
FIT制度 |
FIP制度 |
|
買取価格 |
固定価格 全買い取りが保証されている |
変動価格 |
インバランス |
インバランス特例によって免責される |
発電計画値の報告が義務 |
非化石価値 |
なし |
取引可能 |
インバランスとは、発電の計画値と実績値の差のことを言います。
非化石価値(環境価値)とは、化石燃料を使用せずに発電された電気を取引する市場(=非化石価値取引市場)における環境価値のことです。
10 kW未満/10-50 kW未満の買取価格・期間・申請締切一覧
2025年度の太陽光発電の買取価格と期間、申請締め切りを一覧表で紹介します。
なお、10kW未満は住宅用太陽光発電、10kWh以上は産業用太陽光発電となります。
また時期によって売電価格は変更になるため注意しましょう。
【2025年度 太陽光10kW未満の買取価格・申請締切】
申請期限日 |
適用される調達価格 |
|
2025 年9月 30 日までに |
2025 年6月 30 日(月) |
15 円/kWh(10 年) |
2025 年 10 月1日以降に |
2026 年1月6日(火) |
24 円/kWh(~4 年) |
参考:経済産業省 資源エネルギー庁『2025 年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)』
【2025年度 屋根設置太陽光10kW以上の買取価格・申請締切】
申請期限日 |
適用される調達価格・基準価格 |
|
2025 年9月 30 日までに |
2025 年6月 30 日(月) |
11.5 円/kWh(20 年) |
2025 年 10 月1日以降に |
2025 年 12 月 12 日(金) |
なし |
参考:経済産業省 資源エネルギー庁『2025 年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)』
なお、申請期限日までに申請手続きをおこなっても、提出書類に不備などがあった場合、年度内の認定を受けられないケースもあるため注意が必要です。
自家消費30%要件と例外について
10kW以上50kW未満の事業用太陽光発電の場合、FIT認定を受けるためには、自家消費率が30%以上でなければなりません。
また、災害時などに自立運転ができる機能も必要です。
この要件を満たさない場合は売電の権利を剥奪される可能性があるため注意しましょう。
なお、集合住宅(アパート・マンションなど)に太陽光発電システムを設置する場合は、20kW未満までは自家消費の要件が免除されます。
売電価格の推移と今後の動向

ここでは、これまでの太陽光発電の売電価格の推移と今後の見通しについて解説します。
2012-2025年の買取価格推移と減額率
2012年にFIT制度がスタートしてから現在(2025年度)まで、売電価格はどのように推移しているのでしょうか。
下記は「10kW未満・出力制御対応機器設置義務なし(1kWhあたり)」の売電価格の推移です。
【2012~2025年の買取価格の推移】
- 2012年度 : 42円
- 2013年度 : 38円
- 2014年度 : 37円
- 2015年度 : 33円
- 2016年度 : 31円
- 2017年度 : 28円
- 2018年度 : 26円
- 2019年度 : 24円
- 2020年度 : 21円
- 2021年度 : 19円
- 2022年度 : 17円
- 2023年度 : 16円
- 2024年度 : 16円
- 2025年度 : 15円
参考:経済産業省・資源エネルギー庁『過去の買取価格・期間等』
上記のように、太陽光発電の売電価格は年々引き下げられていることがわかります。
2012年度の売電価格は1kWhあたり42円だったのに対して、2025年度は15円でした。減額率は実に64%にもなります。
電力市場価格との逆転現象と自家消費シフト
太陽光発電による売電価格が下落したことと電力料金の高騰によって、現在は電力会社から買う電気代より太陽光発電システムの売電コストのほうが安くなる「逆転現象」が起きています。
この逆転現象によって、「創った電気を売って儲ける」ことよりも「自家消費をして電気代を節約するメリット」に注目が集まっています。
売電収入と自家消費による節電効果について詳しくは、次項の『売電収入シミュレーション【戸建て4 kW/産業用10 kW】』をご覧ください。
2026年以降の政策見通しと価格予測
前述したように、太陽光発電による売電価格は年々下落しており、今後も買取価格は下がると考えられます。
2025年度の住宅用の売電価格は、FITが開始されてから最安値でしたが、2026年には住宅用の売電価格は1kWhあたり11円まで下がると予想されています。
売電収入シミュレーション【戸建て4 kW/産業用10 kW】

4kWの住宅用太陽光発電システムを導入した場合と、10 kW産業用太陽光発電システムを導入した場合の売電収入はどのくらいになるのでしょうか。
ここでは、それぞれの売電収入・電気料金が高騰した際のROIの変化・蓄電池を利用した際の収益の変化について、それぞれのシミュレーション結果を紹介します。
年間発電量×買取単価で見る収益モデル
まずは、売電価格による収入例を見てみましょう。
4kWの住宅用太陽光発電システムの場合
4kWの住宅用太陽光発電システムの平均発電量は、年間で約4,000kWh~4,500kWh程度と言われています。
たとえば、年間発電量が4,000kWh・自家消費30%( 1,200 kWh )だった場合の売電輸入は次のようになります。(売電価格は2025年度:15円を使用)
2,800 kWh × 15円 = 42,000円
年間の売電収入は42,000円になります。
ただし、太陽光発電システムの発電量は天候条件・経年などによって大きく減少する可能性があることを覚えておきましょう。
10 kW産業用太陽光発電システムの場合
10 kW産業用太陽光発電システムの平均発電量は、年間で約10,000kWhから12,000kWh程度です。
たとえば、年間発電量が10,000kWh・自家消費30%( 3,000kWh )だった場合の売電輸入は次のようになります。(売電価格は、2025年度の屋根設置・10kW以上50kW未満:11.5円/kWh+FIP補助金1円=12.5円を使用)
3,000kWh × 12.5円 = 37,500円
年間の売電収入は37,500円になります。
なお、住宅用太陽光発電システム同様、発電量は天候条件・経年などによって大きく減少する可能性があります。
電気料金高騰シナリオ別のROI比較
ROI(Return on Investment)は、投資した金額に対して、利益率や投資回収期間を判断する際に利用する指標です。
【ROIの計算式】
設置費用 ÷(年間の売電収入+電気代の削減額)=ROI(投資回収年数)
ここでは、前述シミュレーションの数字を使って、電気料金が上昇した際のROI(投資回収年収)の変化を「4kW住宅用太陽光発電システム」を例に計算してみました。
なお、自家消費率(30% 1,200kWh)・基本の電気料金31円/kWh・設置費用(投資額)110万円で計算します。
【基本のROI(投資回収年数)】
設置費用110万円 ÷(年間の売電収入42,000円+電気代の削減額37,200円)
=ROI(投資回収年数)約13.9年
基本の電気料金が31円/kWhの場合、設置費用110万円を回収するには約13.9年かかることがわかりました。
では、電気料金が高騰した場合はどうなるのでしょうか。
【電気料金が年2%上昇(31.6円/kWh)標準的な上昇シナリオの場合】
設置費用110万円 ÷(年間の売電収入42,000円+電気代の削減額37,920円)
=ROI(投資回収年数)約13.7
電気料金が年2%上昇すると投資回収年数は約13.7年となり、基本の回収年数より約2ヶ月短縮されます。
【電気料金が年5%上昇(32.6円/kWh)高インフレシナリオの場合】
設置費用110万円 ÷(年間の売電収入42,000円+電気代の削減額39,120円)
=ROI(投資回収年数)約13.5
電気料金が年5%上昇すると投資回収年数は約13.5年となりました。
基本の回収年数よりが約4ヶ月短縮されます。
このように電気料金が上昇することで、自家消費する電気量の節電額が多くなり、結果的に太陽光発電システムの設置費用の回収期間を短縮できる効果が期待できます。
ただし、インフレなどで電気料金が上昇する場合、そのほかの物価も上昇することが予測できます。
また上記のROIの計算にはランニングコスト(メンテナンス費用など)は反映されていません。
そのため、あくまでシミュレーションとして参考程度に留めてください。
蓄電池併設で収益がどう変わるか
太陽光発電システムで発電した電力を無駄なく使うためには「蓄電池」の併用がおすすめです。
太陽光発電システムは蓄電池を設置しなくても自家消費・売電はできますが、その場合は夜間に消費する電力は電力会社から購入しなければなりません。
特に共働きなどで日中の自宅が無人になりやすい家庭では、太陽光発電で発電した電力を消費しきれないケースもあるでしょう。
しかし、蓄電池があれば消費できなかった電力を貯めておけるため、夜間・雨天時など太陽光発電システムが稼働できないシーンでも蓄電池の電力を消費できるので電気代の節約につながります。
たとえば「4kW住宅用太陽光発電システム(蓄電池なし)・発電量4,000kWh・自家消費率30%」の場合の収益は、以下のようになります。
売電収入 : 42,000円(2,800 kWh×15円/ kWh)
自家消費による節電額 : 37,200円(1,200 kWh×31円/ kWh)
合計 : 79,200円
売電収入と節電額の合計は79,200円になります。
では蓄電池を併設した場合はどうなるのでしょうか。
たとえば、8 kWh蓄電池を併設した場合、年間発電量4,000kWh(約11 kWh/1日)のうち2,920 kWhを自家消費することが可能です。
売電収入 : 16,200円(1,080 kWh×15円/ kWh)
自家消費による節電額 : 90,520円(2,920kWh×31円/ kWh)
合計 : 106,720円
蓄電池を併設することで売電収入と節電額の合計は106,720円となり、蓄電池がない場合と比べて約27,000円も電気代が特になることがわかりました。
蓄電池を併設し、太陽光発電システムで発電した余剰電力を活用するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
ただし、上記の計算には蓄電池の費用やランニングコストを反映していないため、実際の収益とは異なる場合があるため注意しましょう。
太陽光発電の売電を始めるための手続きフロー

ここでは、太陽光発電システムを設置し、FITを利用して売電を始めるまでの流れを紹介します。
なお、アパートや自宅の屋根・駐車場などに太陽光発電システムを設置できることをあらかじめ業者に確認しておきましょう。
売電を始める際の手続き
ここでは、FITを利用して売電を始めるまでの手続きの流れを紹介します。
① 設備認定(JPEA)を受ける
FITを利用するためは、JPEA(日本太陽光発電協会)による太陽光発電設備の「事業計画認定」が必要です。
そのため、まずは必要な種類を揃えて経済産業省資源エネルギー庁に申請します。なお、必要書類については、後述する『必要書類と平均スケジュール 』をご覧ください。
認定審査は主に以下の要件の判断がされます。
- 設備の導入(設計・施工)、運用・管理方法、撤去処分は適切か
- ライフサイクルの設計は適切か
- 長期計画の確実性
② 系統連系契約
事業計画認定後は、電力会社に系統連系申請をおこない、系統連系契約(接続契約)を締結します。
この契約をおこなわなければ売電することができません。かならず太陽光発電システムを設設置した地域を管理している電力会社へ申請し、契約を結びましょう。
③ 施工・検査
太陽光発電システムの設置工事をおこないます。
施工にかかる期間は平均で1週程度ですが、屋外での工事になるため天候によっては完了までに時間がかかる場合があります。
④ 売電開始
太陽光発電システムの設置工事が完了したら、設置業者とともに設備の動作確認をおこないます。問題がなければ発電した電力の売電を開始します。
必要書類と平均スケジュール
ここでは、事業計画認定申請と系統連系契約締結、それぞれに必要な申請書類と平均スケジュールを紹介します。
事業計画認定申請・認定に必要な期間と書類
事業計画認定申請から認定までの期間の目安は1〜3ヶ月と言われています。
しかし、場合によっては認定までにさらに時間が必要になる可能性もあるため、余裕のあるスケジュールを心がけると安心です。
事業計画認定申請に必要な書類は、太陽光発電の出力(10kW未満・10kW以上)によって異なります。ここでは、出力10kW未満の太陽光発電システムの申請に必要な書類を紹介します。
【事業計画認定申請に必要な書類】
- 土地取得の証明書類(登記事項証明書など)
- 建物所有者の同意書類(建物の登記事項証明書など)
- 接続の同意を証する書類(接続契約書など)
- 構造図
- 配線図
なお、業者による申請代行サービスを利用する場合は、委任状・印鑑登録証明書が必要になります。
系統連系契約申請に必要な期間と書類
系統連系契約申請から連系承諾が出るまでの期間の目安は2週間~数か月程度です。
住宅用10 kWh未満の太陽光発電システムの場合、連系承諾までは通常は1ヶ月程度ですが、さらに時間が必要になる可能性もあるため、余裕のあるスケジュールを心がけましょう。
【系統連系契約申請に必要な種類】
- 系統連系申請書
- 系統連系協議依頼表
- 単線結線図
- 付近図
- 構内図
- 主幹漏電ブレーカの仕様資料
- 認定証明書
- 保護機能に整定範囲及び整定値一覧表
必要な種類に不備があると連携承諾が遅くなる可能性もあるため注意しましょう。
計量器(スマートメーター)の設置と読み取り方法
スマートメーターとは、1台で従来の電気の使用量(買電用)メーターと太陽光発電システムの売電用メーターを計測できる計量器のことです。
本来は従来の電気の使用量(買電用)メーターと太陽光発電システムの売電用メーターをそれぞれ設置しますが、スマートメーターであれば1台の設置で済みます。
また、電力使用量と売電量を自動的に計測しデータを電力会社に自動的に送信するため、検針が不要になります。
スマートメーターの見方
スマートメーターの液晶部分には電気の使用量(買電量)と売電量が10秒ごとに切り替わりながら表示されます。 ”矢印” の表示や “丸印” の点滅で、どちらの数値が表示されているかがわかります。
【電気の使用量(買電)の見方】
電気の使用量として表示される電力量は、累積した数値(kWh)です。そのため、1ヶ月分の電気使用量を確認したい場合は、先月末の数値から差し引く必要があります。
【売電量の見方】
売電量として表示される数値(kWh)は、累計の売電量です。そのため、1ヶ月分売電量を確認したい場合は、月末の売電量から差し引いて計算します。
卒FIT後の3つ選択肢

「卒FIT」とは、太陽光発電設備のFIT制度の買取期間が満了することです。
卒FITを迎えると、売電価格が大幅に下がります。そのため、卒FIT後の余剰電力の活用方法を検討することが大事です。
ここでは、卒FIT後の主な選択肢について解説します。
大手電力会社「卒FITプラン」の特徴
卒FIT後の選択肢のひとつが、現状の電力会社に売電を継続することです。
この場合、FIT満了時に自動的に電力会社が提供するプランに切り替わるケースがほとんどです。
手続きや対応の手間などが少ないのがメリットですが、電力会社の買取価格は6~10円程度と、FITの買取価格に比べて大幅に低下するのがデメリットになります。
ただ、電力会社側も売電量を増加させるためにさまざま取り組みをおこなっています。
たとえば、中部電力ではAmazonやWAONと提携し、買取った電力価格の一部をポイントとして還元するサービスをおこなっています。
そのほかにも、一定の条件を満たすことでポイントを付与し、さまざまな商品と交換できるサービスを展開している電力会社も多いです。
新電力/プライベートPPAへの切り替え手順
卒FIT後の選択肢として、新電力(PPS)を検討することも可能です。
新電力会社とは、2016年4月の電力小売全面自由化以降に新規参入した電力会社(小売電気事業者)のことで、他産業からの参入による業者や自治体の第三セクターなどさまざまです。
従来の電力会社よりも、買取価格を高く設定したり、ポイント付与などのサービスを展開したり、魅力的な買取プランを提供しています。
各新電力会社のプランを比較して、自分に合う有利な条件で売電できる会社を選ぶことが大事です。
ただし新電力と契約を結ぶ際は「最低契約期間」が定められる可能性があるため注意が必要です。最低契約期間内は自由に契約を変更することができないため、サービス内容を含めて契約内容をしっかり確認しましょう。
蓄電池+V2Hで “売らずに使う” 選択肢
前述したように、昨今の電気代高騰の影響もあり、太陽光発電システムで発電した電力を売電するよりも、自宅で消費することで節電効果を狙うケースが増えています。
そのため卒FIT後は、太陽光発電システムで発電した全電力を自家消費するという選択肢も生まれます。
その際におすすめなのが「蓄電池とV2H」の併用です。
蓄電池は、太陽光発電システムで発電した電気を充電できる装置のことです。
蓄電池を併設することで、夜間・雨天時など太陽光発電システムが稼働できないときでも蓄電池の電力を使用できるため、節電につながります。
V2Hとは「Vehicle to Home(ヴィークル・ツー・ホーム)」のことで、電気自動車(EV ・PHEV)に直接充電したり、車両に貯められた電気を自宅へ給電したりといった機能を持つ設備やシステムのことです。
なお、V2Hそのものには充電機能はありません。
V2Hを蓄電池代わりに利用したい場合はEV・PHEVを経由する必要があります。そのため、EV・PHEVを使用中は自宅などへの電力供給はできません。
蓄電池とV2Hを併用することで大容量の電気を充電できるため、卒FIT後の太陽光発電システムで発電した電力を無駄にすることなく自家消費することが容易になります。
太陽光発電の売電収入を最大化するコツ

ここでは、太陽光発電システムの収益を最大化するためにできることを紹介します。
発電量を伸ばす設置角度・方位・メンテナンス
太陽光発電システムによる発電量が増えれば売電収入も増加します。
そのためには、ソーラーパネルを選ぶ際や設置する際は、発電能力が最大になるよう次のポイントをチェックしましょう。
- パネルのメーカー・種類
- 必要なパネルの枚数
- 設置位置
- 設置の方角
- 設置角度
上記のポイントをしっかりとチェックしたうえで、発電量のシミュレーションをおこなうことが大事です。
蓄電池導入で自家消費率を上げる方法
直接の売電収入にはつながりませんが、太陽光発電システムで発電した電力の自家消費量を増やすことで節電でき、結果的に得になります。
自家消費量を増やすためには、蓄電池の併設が欠かせません。
蓄電池の容量は、設置している太陽光発電システムで発電できる電力量や自家消費電力量をなどから最適な容量の蓄電池を選ぶとよいでしょう。
また節電効果を上げるために、必要に応じて断熱リフォームなどをおこなうのも効果的です。
青色申告・減価償却で手取りを増やす節税テク
太陽光発電システムで売電した場合、年間の売電所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
確定申告では、太陽光発電システムの導入費用を減価償却費として計上できるため、収益が圧縮され、結果的に節税につながります。
また、青色申告で確定申告をおこなうと以下の節税効果が期待できます。
- 個人事業主の場合、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられる
- 白色申告に比べて経費として計上できる範囲が広い
- 赤字が出た場合、3年間繰り越して翌年以降の所得から控除できる
なお、売電で得た収入は「事業所得」または「雑所得」になります。
太陽光発電の売電時によくあるトラブルと対策

ここでは、太陽光発電システムに関する売電時によくあるトラブルと対策方法を紹介します。
発電量低下(パネル汚れ・PCS故障)のチェックポイント
ソーラーパネルは屋外に設置されているため、砂埃・鳥の糞・枯葉などによる表面ガラスの汚れや、パネル内部の配線などの劣化・断線などが原因で発電効率が下がってしまう可能性があります。
またPCS(パワーコンディショナ)の劣化・故障により発電量が低下するケースも考えられます。
PCSとは、太陽光発電システムで発電された直流電力を、家庭などで使用できる交流電力に変換する装置です。
PCSの変換効率が高いほど太陽光発電で発電した電力を無駄なく利用できます。そのため、PCSに不具合があると変更効率が下がってしまい、結果的に発電量が低下するのです。
こういったソーラーパネルやPCSなどの不具合を放置しておくと発電量が低下するだけでなく、大きな故障につながるおそれもあります。
太陽光発電システムの発電量の低下を防ぐためにも、専門業者に定期的にメンテナンスしてもらうようにしましょう。
買取単価の誤請求と検針ミスへの対処
太陽光発電の売電時によくあるトラブルとして、「買取単価の誤請求」と「検針ミス」があげられます。
どちらの場合も、まずは契約している電力会社に状況を詳しく説明し、事実確認を依頼しましょう。
電力会社が誤請求や検針ミスを認めた場合、差額の返金や次回以降の請求にて調整などの対処方法が提示されます。
対処方法や差額に納得できない場合は、再交渉や第三者機関(消費生活センター、電力・ガス取引監視等委員会など)への相談を検討するとよいでしょう。
反射光・景観クレームを回避する設計
ソーラーパネルの反射光・景観に関するクレームに関するトラブルは、近隣住人の生活に支障をきたすおそれもあるため注意が必要です。
おもなクレームの内容は、ソーラーパネルが反射する太陽光が眩しい・熱を感じる・周囲の景観が悪いなどです。
こういったクレーム対策としては、太陽光発電システムを設置する前に、パネル反射光の影響をシミュレーションし、周辺に悪影響が出ないように設置場所や角度を検討することが重要です。
ソーラーパネル設置後にクレームになった場合は、ソーラーパネルに反射防止フィルムを貼ったり、周囲に木を植えたりすることで、反射光の遮断や景観を保つことにつながります。
太陽光売電で活用できる補助金・優遇策(2025年度版)

太陽光発電システムの設置には、国や地方自治体の補助金制度・優遇策などを活用できる場合があります。
太陽光発電システムの設置費用は高額になるケースもあります。補助金などを上手に利用して初期費用をおさえることができれば、それだけ収益を増やすことにつながります。
ここでは、主な補助金制度や優遇策などを紹介します。
国の再エネ導入促進補助(太陽光+蓄電)
現在、住宅用太陽光発電の導入に対する国からの補助金制度は「2014年に廃止」され、法人向け太陽光発電にのみ、以下の補助金が交付されております。
【ストレージパリティ補助金(環境省)】
- PPA・リース(業務用・産業用・集合住):5万円/kW、(戸建て住宅):7万円/kW
- 自己所有(業務用・産業用・集合住):4万円/kW
- 定置用蓄電池(業務・産業用):3.9万円/kWh
- 定置用蓄電池(家庭用):4.1万円/kWh
*補助上限:太陽光発電設備2,000万円、蓄電池・充放電設備1,000万円
*公募中期間:(二次・一次公募)令和7(2025)年6月5日~令和7(2025)年7月4日
参考:一般財団法人環境イノベーション情報機構『【公募のお知らせ】令和6年度(補正予算)および令和7年度予算二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の公募について』
自治体の上乗せ補助・利子補給
各地方自治体では、太陽光発電システムの設置に対してさまざまな補助金が交付されています。
たとえば東京都では、『災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業』として、太陽光発電・家庭用蓄電池・V2Hなどの設置に対して、それぞれ補助金制度を設けています。
新築住宅に太陽光発電を設置する場合、ソーラーパネル設置容量1kWあたり10万円(最大500万円)と非常に高額です。(適用条件あり)
参考:東京都『災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業』
補助金の対象や適用条件、補助金額については、各市区町村により異なります。
太陽光発電システムの新規設置・交換を検討する場合は、居住地の自治体窓口またはホームページなどで確認するとよいでしょう。
固定資産税1/2軽減など税制優遇
太陽光発電システムを所有していて要件に適用される場合、「固定資産税の課税標準額の特例措置」の対象となります。
固定資産税が課せられることになった年度から3年分の固定資産税にかぎり、課税標準が以下の割合に軽減されます。
【太陽光発電 固定資産税の特例措置】
対象者:再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者
- 発電出力が1,000kW以上 : 3/4
- 発電出力が1,000kW未満 : 2/3
参考:経済産業省 資源エネルギー庁『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)』
なお、出力10kW未満の住宅用太陽光発電設備の固定資産税は基本的に非課税です。
ただし、賃貸物件や店舗併設住宅で利用する場合は事業用資産とみなされるため、課税対象となることがあります。
太陽光発電の売電に関するよくある質問(FAQ)

ここでは太陽光発電システムについて、よくある質問をまとめました。
Q:売電収入にかかる税金は?
A:太陽光発電システムで発電した電力を売却し利益を得て、売電所得が年間20万円を超える場合は所得税が課されるため、確定申告が必要です。(売電所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です)
なお、売電所得は「売電収入から必要経費(ランニングコストなど)を差し引いた金額」であり、売電収入そのままではありません。
Q:途中でFIPに移行できる?
A:FIP認定の対象(太陽光発電の場合は10kW以上)であれば、すでにFIT認定を受けた再エネ発電事業であっても、FIPへ移行することができます。
ただし、FIP制度はFITのように売電価格が固定ではないため、収益の予測がむずかしくなる可能性があります。
そのため、市場の動向を把握したうえで、需要と供給のバランスを考慮した売電戦略が必要です。
Q:屋根修繕が必要になった場合の対応は?
A:太陽光発電システムを設置している屋根を修繕(大規模修繕)する場合、屋根を塗装する、または重ね葺き(カバー工法)の2種類があります。
屋根塗装の際は、ソーラーパネルを一時撤去する場合と撤去せずにそのままの状態で工事をおこなう方法があります。
建物の築年数が10年程度の場合、太陽光パネルを一時撤去せずに、パネルを設置していない部分のみを塗装するのがおすすめです。
また重ね葺き(カバー工法)は、既存の屋根の上にガルバリウム鋼板などの新しい軽量な屋根材を葺く方法です。
建物の築年数が20年以上になると屋根が雨漏りするケースも増えるため、塗装ではなく、重ね葺き(カバー工法)で修繕がおこなわれるケースが多くなります。
その場合はソーラーパネルを一時撤去して工事をおこなうことになります。
なお、ソーラーパネルを一時撤去するには脱着費用が発生します。
脱着費用はパネルの枚数などによって異なりますが、目安は20万円程度からです。また別途、足場代は必要です。
まとめ
2025年度の太陽光発電の売電価格は1kWhあたり15円と、2012年度の売電価格は1kWhあたり42円からみると、大きく下落しています。
そのため、売電目的ではなく、自家消費する「節電」を目的として太陽光発電システムを検討する人も増えているようです。
その場合は、太陽光発電システムに蓄電池やV2Hを併設することで、発電した電力を無駄なく自家消費することが可能になります。
太陽光発電システムを導入する場合は、売電や自家消費、卒FIT後の選択などを考慮したうえで検討しましょう。
この記事を読んだ方に人気のお役立ち資料一覧
>>アパート経営シミュレーション無料エクセルソフト5選
>>カテゴリー別おすすめアパート建築会社一覧
>>大家さん必見の空室対策アイデア10選
>>アパートWiFi導入のメリット&デメリット
>>入居者募集テクニック8選