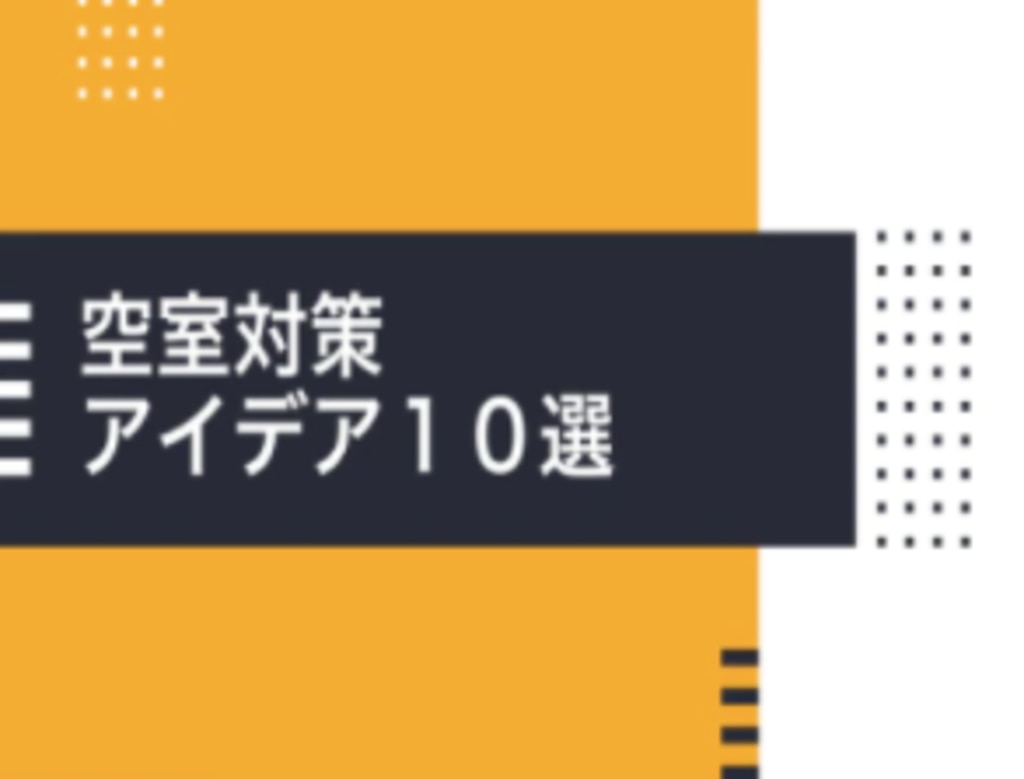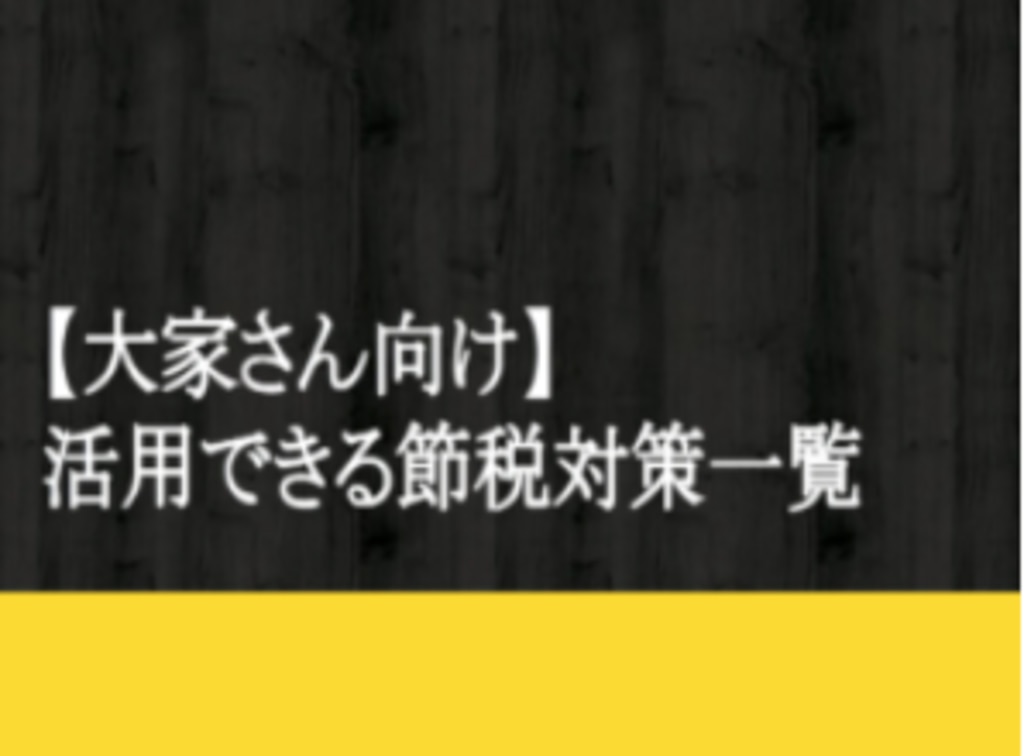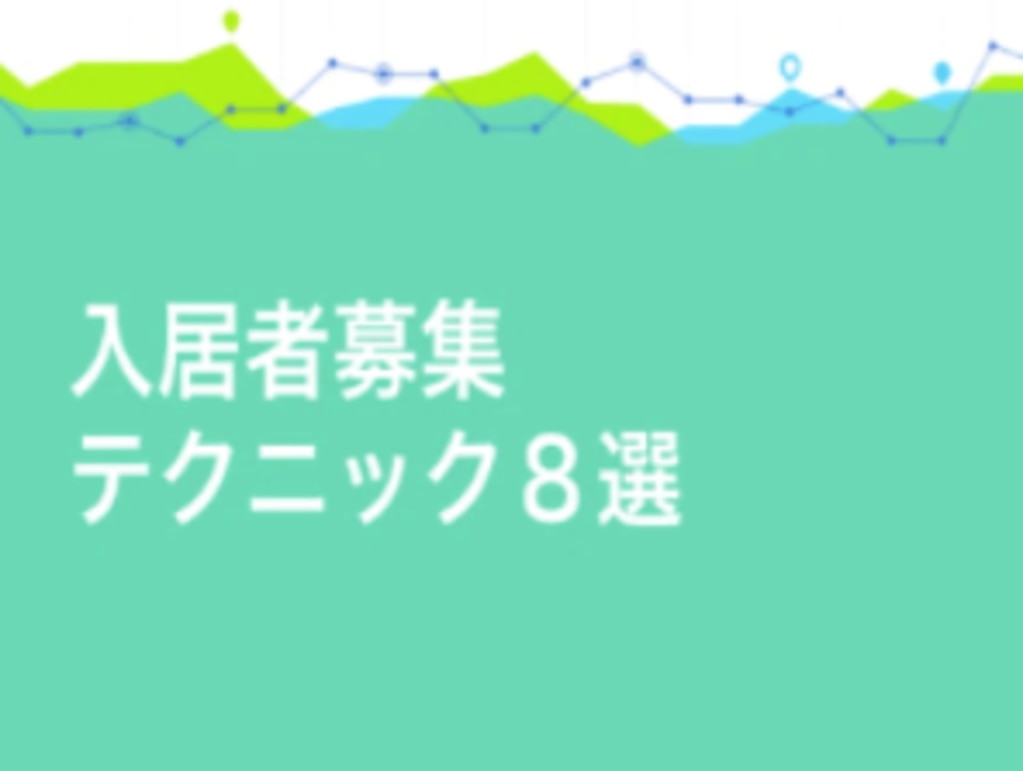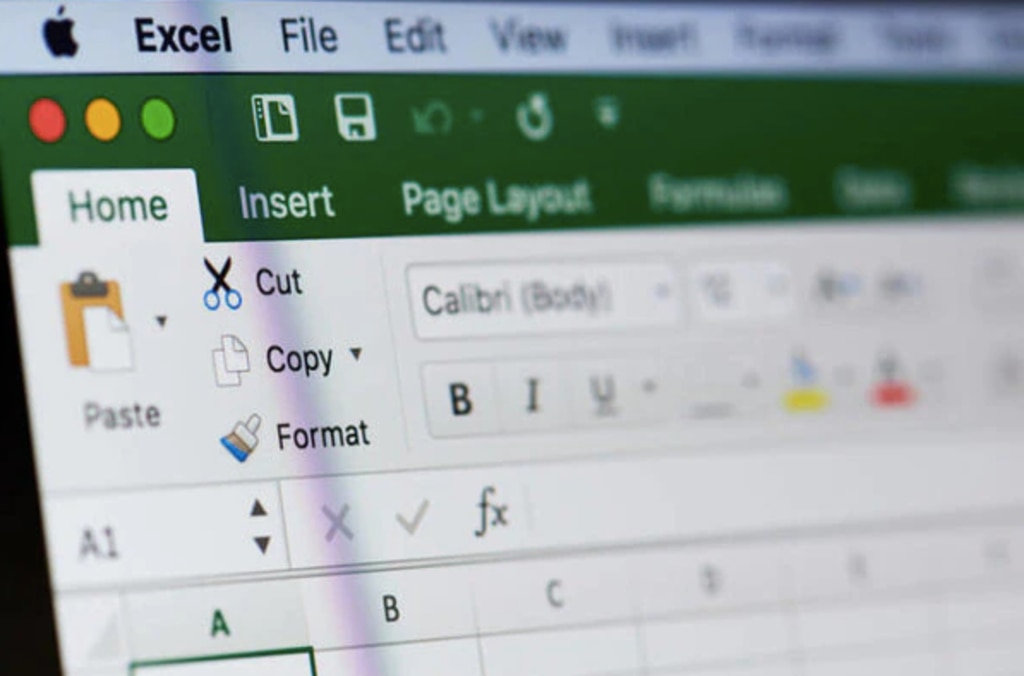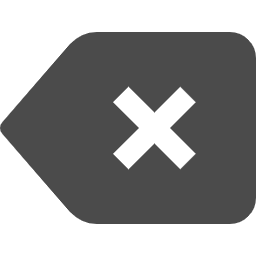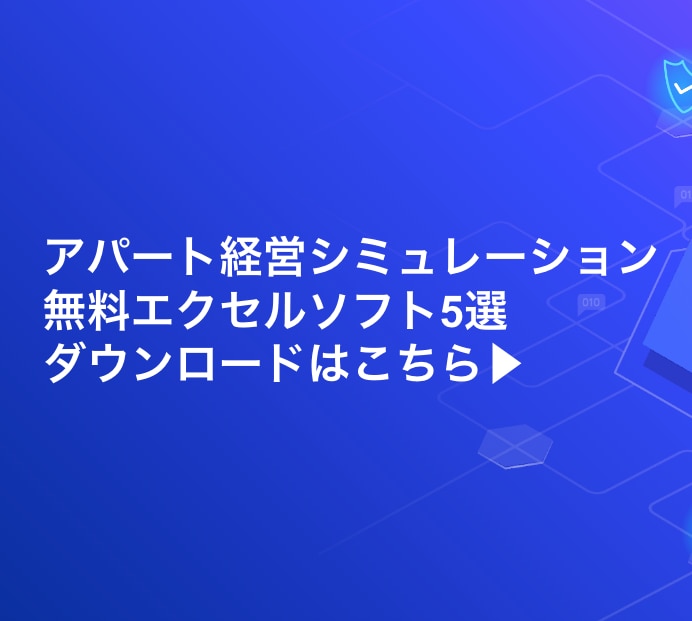アパートの耐用年数とは?減価償却費を正しく計上して節税効果を上げよう

もしあなたがアパート経営の初心者であれば、「耐用年数」「減価償却費」という言葉を聞いたことはあるけれど、詳しくは説明できないかたが多いのではないでしょうか。
耐用年数も減価償却費も経費やローンに関わる重要なもの。アパート経営をする場合にはきちんと理解することが大切。
今回はこちらの記事では、アパート経営において耐用年数と減価償却費の関係をわかりやすく説明します。
また節税に効果的な減価償却費の経費計上についても詳しく解説します。しっかり学んで効率的なアパート経営を目指しましょう。
大家さん向けの節税対策一覧資料を見たい方はこちら
目次[非表示]
- 1.アパートの耐用年数とは?
- 1.1.耐用年数は法律で決まっている
- 1.2.耐用年数と減価償却費について
- 1.3.耐用年数は融資期間に大きく関わる
- 2.アパート経営に関わる建物・設備など資産の耐用年数一覧
- 3.LAN設備(インターネット設備)は資産の一部として計上できる
- 4.LAN設備(インターネット設備)の耐用年数について
- 4.1.LANケーブルの耐用年数
- 4.2.ハブ・ルーター・LANボード・リピーターの耐用年数
- 4.3.物理サーバーの耐用年数
- 5.減価償却費を正しく計上して節税効果を上げよう
- 5.1.減価償却費は最大限計上する
- 5.2.減価償却できる資産の種類ごとにわけて計上する
- 6.法定耐用年数よりも長い建物の寿命!さらに長生きさせるには?
- 7.まとめ
アパートの耐用年数とは?

アパート経営における耐用年数とはなにを指しているのでしょうか。 建物ばかりでなくアパートに付属している設備や構築物、器具備品についてそれぞれに耐用年数が設定されています。
耐用年数は法律で決まっている
耐用年数とは税務上法律で決められている「法定耐用年数」のこと。建物の寿命ではありません。
長期にわたり使用する所有物の価値を経費として毎年少しずつ計上するために、国税庁によって種別ごとの耐用年数が定められています。
国税庁では確定申告書作成のために耐用年数の一覧表をホームページで公開しています。
参考:国税庁 耐用年数表
耐用年数はアパート本体だけでなくアパートに付属している設備や構築物、器具備品にも設定されています。またアパート本体の構造によって、設定される耐用年数が変わってきます。例えば木造の場合は22年となっています。
耐用年数はローンの年数とも関わってくるため、アパートの建築を計画する際には構造についてしっかり確認すべきですね。
耐用年数と減価償却費について
アパートは購入してから長期間かけて使用されます。アパート本体だけでなくアパートに付属している設備や構築物、器具備品も同様ですね。
そのためアパート事業ではアパート本体やその付属物について、長期間少しずつ経費として計上できる仕組みがあります。その仕組みのことを「減価償却」といいます。
減価償却費を決めるのがそれぞれの耐用年数です。この減価償却費が、アパート経営の節税においてとても重要な役割を果たします。
耐用年数は融資期間に大きく関わる
耐用年数にはもうひとつ働きがあります。それはローンの融資期間を決めるものです。
融資をする金融機関は、もしローン返済が滞ってしまい返済不能になってしまった場合、抵当権を実行してアパートを売却して残債に充てることになります。
その際に耐用年数を過ぎてしまったアパートであれば当然売却が困難になるため、法定耐用年数を超えて融資期間を設定することはまずありません。
注意したいのは、実際には法定耐用年数より融資期間が短くなるケースが多いことです。 たとえば木造のアパートの耐用年数は22年ですが、融資期間は短縮されて20年というケースは珍しくありません。金融機関との取引実績などにもよりますが、融資期間は耐用年数より短くなると想定しておいたほうがいいでしょう。
アパート経営に関わる建物・設備など資産の耐用年数一覧

アパート建物本体はその構造によって法定耐用年数が変わってきます。特に鉄骨造は骨格材の厚みによってこまかくわかれているので注意しましょう。
以下にアパートの建物本体、アパートに付属している設備や構築物、器具備品の耐用年数の一覧を記載します。いずれも新築であり住居用とします。
建物(建物本体)
種別 |
耐用年数 |
木造 |
22年 |
鉄骨造 骨格材の厚み3mm以下 |
19年 |
鉄骨造 骨格材の厚み3mmを超え4mm以下 |
27年 |
鉄骨造 骨格材の厚み4mm以上 |
37年 |
鉄筋コンクリート造 |
47年 |
鉄筋コンクリート造のアパートは木造アパートの倍以上の耐用年数となっています。また鉄骨造のアパートは骨格材の厚みによって耐用年数は大きく異なります。
ちなみに、建物本体のなかには一体化した設備や備品も含まれていることに注意。
たとえばお風呂(ユニットバスまたは浴槽)、下駄箱、フローリングといった設備や備品は建物と一体化したものとみなされ、減価償却も同時におこなわれます。
建物付属設備
種別 |
耐用年数 |
電気設備のうち蓄電池電源設備 |
6年 |
上記以外の電気設備 |
15年 |
給排水設備 |
15年 |
衛生設備 |
15年 |
ガス設備 |
8年 |
排煙または災害報知設備 |
8年 |
蓄電池電源設備はオール電化でもなければアパートにはあまり使われることがありません。給排水設備や衛生設備とは、水回りの配管、トイレの本体およびその配管を指します。
構築物
種別 |
耐用年数 |
通信ケーブル(光) |
10年 |
通信ケーブル(光以外) |
13年 |
フェンス・へい(金属製・木製) |
10年 |
舗装路面(アスファルト) |
10年 |
最近は無料インターネットなどを導入するアパートも多いため、はじめから通信ケーブルが配線されています。光ケーブルとそれ以外で耐用年数が変わります。
器具備品
種別 |
耐用年数 |
冷房、暖房、通風設備 |
6年 |
キッチンシンク |
5年 |
ガス器具 |
6年 |
クロス(壁紙) |
6年 |
床類(じゅうたん、畳床、クッションフロア) |
6年 |
インターフォン |
6年 |
エアコンなどの器具備品は購入金額によって計上の仕方が変わるので注意しましょう。
- 購入金額が10万円未満の場合:購入時の経費として一括計上
- 購入金額が10万円以上20万円未満の場合:いったん計上して3年間均等償却
- 購入金額が20万円以上の場合:耐用年数で減価償却
寒冷地ではエアコンではなくボイラーを使用しているアパートもありますが、冷暖房用ボイラーの耐用年数は13年から15年でワット数によって異なります。
クロスや床材といった内装は耐用年数6年となっていますが、そのうちフローリングだけは別です。フローリングについては建物と一体化したものとして減価償却も建物と一緒に行われます。
LAN設備(インターネット設備)は資産の一部として計上できる

LAN設備(インターネット設備)を導入した場合、資産の一部として計上できます。
ここでは、LAN設備をどう計上するのか、レンタルサーバーやクラウドサーバーなどの経費計上についても紹介します。
LAN設備は「固定資産」で計上可能
LAN設備は基本的に勘定科目の「固定資産」として計上できます。
そのためアパート建物や建物付属設備と同様、耐用年数が定められており、減価償却して毎年少しずつ経費として計上していきます。
ただしLAN設備は複数の機器などで構成されているため、その機器ごと(LANケーブル、サーバー、ルーターなど)それぞれに耐用年数が設定されているため、「LAN設備」としてひとかたまりで計上することができません。
よってLAN設備を減価償却する際は、構成する機器について、それぞれ個別に減価償却費を計算していく必要があります。
ただし、減価償却の対象となるのは「購入代金が10万円以上のもの」です。LAN設備の購入総額が10万円未満の場合は、購入した年度の決算で一括処理が可能です。
なお「少額減価償却資産の特例措置」が、令和4年度税制改正において、適用期限が2024年(令和6年)3月31日まで延長されました。
これは中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した際に、取得価額相当額を損金の額に算入できる税制措置です。特例が適用される上限額は、その事業年度中に購入した少額減価償却資産の合計額300万円までとなります。
通常の減価償却でも、最終的には取得費は損金となりますが、法定耐用年数にわたって費用計上するため全額が損金となるまでに時間がかかります。
少額減価償却資産の特例措置に適用すれば、一括費用計上できるため節税効果を得られます。
レンタルサーバーやクラウドサーバーは経費計上が可能
レンタルサーバーやクラウドサーバーは経費として計上可能です。これらは利用者が購入したものではなく、サービス提供元のプロバイダーの所有物とみなされるため、資産ではなく経費として計上します。
そのためレンタルサーバーやクラウドサーバーは減価償却が不要であることをおぼえておきましょう。
なお後述しますが、物理サーバーは資産となるため減価償却が必要になります。
LAN設備(インターネット設備)の耐用年数について

LAN設備の減価償却をおこなう場合は、構成している機器など、それぞれの耐用年数も把握しておく必要があります。ここでは、機器それぞれの耐用年数について紹介します。
参考:国税庁『LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答』
LANケーブルの耐用年数
LANケーブルの耐用年数は18年です。ちなみに同じケーブル類でも光ケーブルの耐用年数は10年となっており、それぞれ耐用年数が異なります。
LANケーブルとは、パソコンとルーターを接続して有線LAN接続をおこなう際に用いられるケーブルです。
通信の安定性や速度を重視するのであれば、無線LANよりも有線LANが優れています。LANケーブルは有線LAN接続には欠かせない機器のひとつです。
なお、18年という数字は法律上の耐用年数であり、適切な状態で管理すれば20年から30年程度の利用も可能です。ただし、LANケーブルが劣化すると通信速度が遅くなる場合もあります。
無理にねじ曲げたり、圧迫したり、引っ張ったり、絶え間なく振動が起こったりしている環境ではLANケーブルのダメージも大きく、劣化のスピードは速くなるため注意が必要です。
またケーブルの規格が古い場合は、モデムやルーターが高性能でも本来の通信速度が発揮できないことがあります。使用しているインターネット回線の通信速度に対応するLANケーブルを使いましょう。
ハブ・ルーター・LANボード・リピーターの耐用年数
ハブ、ルーター、LANボード、リピーターは、LAN設備を構築する際に必要なネットワーク機器です。耐用年数は、それぞれ10年に設定されています。
各機器の役割は以下のようになります。
・ハブ:複数のLANケーブルを繋げる集束装置
・ルーター:ケーブルでモデムに接続してインターネット通信をおこなう機器
・LANボード:コンピュータに装着して機能を追加する拡張カードの一種で、LANに接続を追加するための板状の基盤
・リピーター:電気信号の中継器であり、電気信号を受信し弱まったりノイズが入ったりした信号を増幅・整形して元の信号に戻す役割を持つ機器
ただしこれらの機器は技術革新が盛んなため、10年間継続して使用するのは現実的ではありません。およそ5年から6年程度で新規購入、または刷新するのが一般的です。
途中で処分した機器の減価償却は不要となるため、必要に応じて買い替えをおこないましょう。
物理サーバーの耐用年数
サーバーの耐用年数は6年です。ただしこれは物理サーバーのみが対象で、前述したようにレンタルサーバーやクラウドサーバーなどは経費として計上可能です。
その場合、減価償却は不要なので、会計処理の負担を減らしたいのであればレンタルサーバーやクラウドサーバーの利用がおすすめです。
なお物理サーバーは使用年数が経過するにつれて故障する可能性が高まり、データが消失してしまう可能性があります。
そのため耐用年数が切れる6年に合わせて、老朽化したサーバーを新しいものに取り替え、データを適切に利用できるようにする「サーバーリプレース」されることも少なくありません。
減価償却費を正しく計上して節税効果を上げよう
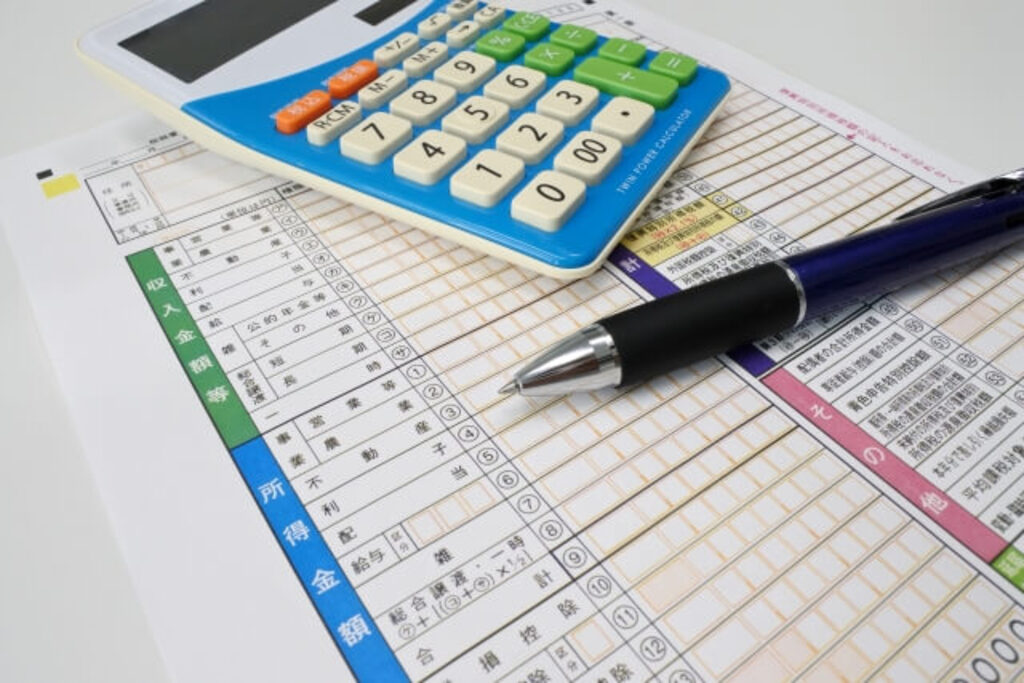
アパート経営において所得税の節税は重要な課題です。減価償却費を経費として計上することで大幅な所得の軽減ができるため、減価償却費についてしっかりと理解しておきましょう。
減価償却費は最大限計上する
アパートを購入したら、確定申告で前年度の収入と経費を申告します。この経費にあたるのが減価償却費。減価償却費を最大限に計上することで所得を軽減し、所得税を節税することが可能。
また減価償却費の計算の仕方は新築物件と中古物件で異なります。新築物件の場合は単純に法定耐用年数で割りますが、中古物件の場合は下記の計算式になります。
- 法定耐用年数を超えている場合
耐用年数=法定耐用年数×20%
- 法定耐用年数が残っている場合
耐用年数=残存法定耐用年数+(経過年数×20%) 減価償却費の計算方法は定額法と定率法の2種類あります。
- 定額法:資産の所得価格を耐用年数で均等に配分する方法
- 定率法:資産の未償却残高に耐用年数ごとに定められた率をかけて計算する方法
アパートの建物と建物付属設備については定額法で計算します。等分にわけて計上するため減価償却費は初年度に計上した金額が毎年つづくことになります。最初の確定申告でしっかりと計上することが大切ですね。
減価償却できる資産の種類ごとにわけて計上する
減価償却費を経費として多く計上するためには、できるだけ資産を種類ごとに分解することが重要です。
前項で解説した建物付属設備や構築物、器具備品といった項目は、建物本体に比べて耐用年数が短いもの。つまり、これらを経費計上することで所得が高くなりがちな最初の10年から15年の間、所得税を軽減することができるのです。
建物一括で計上するより資産の種類ごとにわけて計上することで節税になりますので、しっかり分解して計上しましょう。
法定耐用年数よりも長い建物の寿命!さらに長生きさせるには?

法定耐用年数というのは税務上で使用する目安のようなもので、実際の建物の寿命とは異なります。
実際に賃貸の市場をみてみると築22年を超えたアパートは多数あり、中には築30年を超えているものも少なくありません。しかし一方で、築30年前後には取り壊しや建て替えとなっているアパートもみられます。
アパートの建物としての寿命を延ばすには、適切なメンテナンスが不可欠です。メンテナンスで重要なのは水回りの事故や侵入(水漏れや雨漏り)を防ぐこと。定期的な水回り設備の点検や修繕。そして外壁や屋根の手入れが必要です。
メンテナンスをしっかりとすることで、法定耐用年数を超えて長生きできるアパート経営が可能になるでしょう。
まとめ
アパート経営において減価償却費をきちんと計上することは節税につながる大切なものです。法定耐用年数とはその減価償却費を決定するものなので、アパートを購入する場合にはしっかりと事前にシミュレーションしましょう。